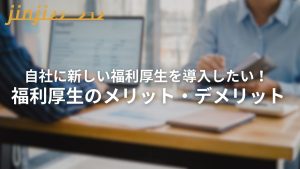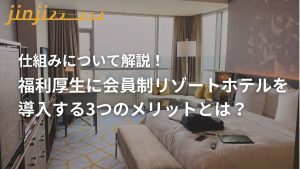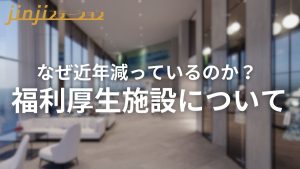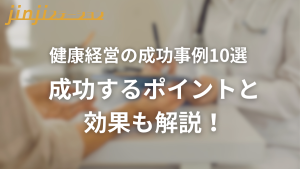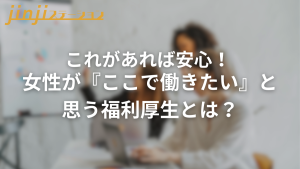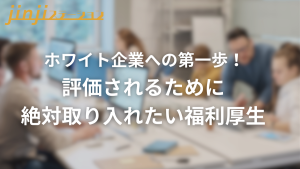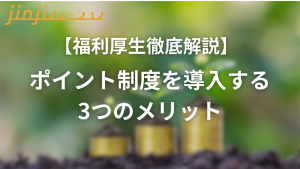福利厚生費とは、従業員が働きやすくなるように、会社が負担する経費のことです。この費用は、健康や生活を支えるために使われ、従業員の満足度を向上させる重要な役割を果たします。しかし、運用方法を誤ると「従業員に十分に響いていない」「本来得られるはずの節税効果が薄い」といった課題が生じることがあります。
そこで、この記事では、福利厚生費について、計上するための要件や、注意すべきポイントについて解説します。ぜひこの記事を読んで、今の運用を見直し、より効果的な福利厚生制度を作るきっかけにしてみてください!
福利厚生費とは?
福利厚生費とは、会社が従業員の働きやすい環境をつくるために、給料やボーナスとは別に使うお金のことです。このお金は、従業員の生活や健康、仕事をしやすくするために使われます。例えば、取引先との接待や仕事で必要な道具の購入には使われませんが、従業員の健康や生活を支えるための費用には使われます。また、条件を満たすと税金の計算で経費として扱われ、会社の税金負担を軽くする効果もあります。
会議費・交際費・雑費…間違いやすい勘定科目との違いは?
経費処理の中でも特に迷いやすいのが、会議費・交際費・雑費といった「似ているようで違う」勘定科目の扱い。ここを間違えてしまうと、後から“これは経費じゃありません”と否認され、修正の手間がかかったり、そのまま放置をしていると追徴課税の対象になるケースも…。
そこで今回は、特にまちがえやすい「会議費・交際費・雑費」の違いについて一緒にみていきましょう。
交際費との違いは?
「社内向けか社外向けか」「接待があるかどうか」がポイント!交際費とは、基本的に社外の取引先やお客様との関係づくりにかかる費用のこと。逆に、社内だけの交流やイベントにかかった費用は交際費とは言えません。
- 会社のみんなで開く忘年会 → 福利厚生費
- 取引先とのランチや飲み会 → 交際費
このように、“誰と”の部分がどちらに分類されるかのカギになります。社外の方が対象で、接待の要素があれば交際費にするのが基本です。
会議費との違いは?
業務上の打ち合わせか、飲食がメインかをチェック!会議費は、社内外を問わず「業務に必要な話し合い」を目的とした費用です。そこに軽いお茶やお菓子がついていても、会議がメインであれば問題ありません。
ただし、食事の内容によっては「それ、本当に会議なの?」と疑われることも…。
- 会議中に出すお茶やお菓子 → 会議費
- お弁当やランチがメインになっている → 福利厚生費にあてはまる可能性も
“会議のお供にちょっとした飲み物”くらいなら会議費でOKですが、食事が主役になってしまうと違う費目になることもあるので注意しましょう。
雑費との違いは?
「とりあえず雑費」はNG!雑費は、どの費目にも当てはまらないような“イレギュラーな支出”を処理するための、いわば「最後の手段」のような科目です。でも、「よくわからないから雑費にしておこう」となんでも放り込んでしまうのは危険です。
- 社員レクリエーションの費用 → 福利厚生費
- 社内で使う備品の購入 → 消耗品費や備品費
雑費には、「どの科目にも分類できない特別な支出」だけを入れるのが正解です。税務調査では、雑費の内容は特に細かくチェックされやすいポイントでもあるので、できるだけ具体的な科目に振り分けるクセをつけておくと安心です。

実際に、経費全体の中で雑費が多すぎた会社が「これは何の支出ですか?」とすべて説明を求められたことも…その結果、説明が不十分だったものは「経費とは認められません」と判断され、追徴課税になったケースもあるんです。
「雑費」は便利なようでいて、実は“最も注意が必要な科目”のひとつでもあるんです。
福利厚生費の種類
福利厚生費には法律で支払いが義務付けられている「法定福利費」と会社が独自に設定している「法定外福利費」の2種類があります。原則、法定福利・法定外福利のどちらも課税されません。
1. 法定福利費
法律で支払いが義務付けられている費用のことです。会社が負担する主なものは以下の通りです
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料(全額を会社が負担)
- 介護保険料
これらは、従業員が会社に勤める際に必要な保険料で、会社が一部または全額を支払います。
2. 法定外福利費
法定外福利費は、会社が独自に設定している福利厚生費用です。法律で義務付けられていないため、内容は会社によって異なります。次のようなものが含まれます
- 社宅の家賃補助
- 通勤手当
- リモートワーク手当
- 慶弔見舞金(結婚やお悔やみの際の手当)
- 家族手当
- 社員旅行や忘年会、新年会の費用
- 健康診断の費用
- 食事補助(社員食堂やランチ代の補助)
- 自己啓発手当(スキルアップのための費用補助)
福利厚生費を経費計上するための3つの要件
福利厚生費は非課税のため、企業の税金対策としても有効です。ただし、どのようなものでも経理上、福利厚生費として計上できるわけではありません。計上するためには、3つの条件を満たす必要があります。
- 全従業員に対して公平に適用されていること
- 社会通念上妥当な金額であること
- 現金支給ではないこと
以下で詳しく解説します。
全従業員に対して公平に適用されていること
福利厚生費を非課税扱いにするためには、全従業員に対して公平に適用されている必要があります。一部の従業員や正社員だけに適用されている場合、福利厚生費としての計上はできません。
例えば、役職者だけで旅行に行っている、特定の部署の従業員だけに書籍購入費を支給しているといった場合、その費用は福利厚生費として認められません。
社会通念上妥当な金額であること
福利厚生費として計上するには、従業員が受ける経済的な利益が、社会一般的に見て妥当な水準である必要があります。極端に高額な金額や一般的な範囲を超えた豪華な内容の福利厚生は、給与とみなされ課税対象となります。
例えば、従業員向けの保養施設であっても、一泊数十万円もするような高級リゾートホテルは、社会通念上妥当な金額を超えていると判断される可能性があります。
現金支給ではないこと
福利厚生費として認められるためには、従業員に提供されるものが現金や換金性の高いもの(現金に換算しやすいもの)であってはいけません。 換金性の高いものとは、ギフト券、プリペイドカード等を指します。
これらの支給は、従業員が自由に使うことができ、実質的に給与と変わらないと判断されるため、福利厚生費として認められず、課税対象となってしまいます。
課税対象になる福利厚生費のパターン
ここでは、課税対象になりやすい福利厚生費のパターンを3つご紹介します。
通勤手当
通勤手当は、従業員が仕事のために通勤する際に必要な交通費を会社が負担する福利厚生制度です。従業員の負担を軽減する福利厚生費ですが、支給額によっては課税対象になる可能性もあります。
例えば、電車やバスといった公共交通機関を利用している場合、上限額は月15万円です。自家車で通勤する場合は、2km未満であれば全額非課税。2km以上になると、距離に応じた上限金額が定められます。なお、通勤手当に関しては、例外的に現金での支給が認められています。
社宅や食事補助も同様に上限金額がある点に注意してください。
研修旅行や社員旅行費
業務に関連する研修旅行の場合は、業務に必要な知識や技術を習得するための旅行であれば、福利厚生費として認められます。しかし、業務と関係ない観光旅行の場合は、単なる旅行とみなされ、福利厚生費として認められません。旅行が福利厚生と認められるためには、以下の条件を満たす必要があります
- 4泊5日以内の旅行であること
- 従業員の半分以上が参加していること
また、参加しない社員に現金や換金性の高いものを支給した場合は課税対象となります。
参照:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁
健康診断
健康診断費用を会社が直接負担する場合は、法定健診・法定外健診ともに非課税です。一方、健康診断の費用を現金で支給する場合は、給与とみなされるため課税対象となります。
また、健康診断を福利厚生とする場合は、すべての従業員に対して公平に権利を与える必要があります。特定の雇用形態や性別、役職のみを対象とする健康診断は、課税対象となるため注意しましょう。
認められないケース
高額すぎる人間ドック(オプション付きなど)
法定健診の範囲であれば問題ありませんが、一般的ではない高額オプション検査や付加サービス付きの人間ドックなどになると、会社が負担した費用の一部が給与とみなされることがあります。「健康管理の一環だからOK」と思っていても、相場を大きく超える検査内容には注意が必要です。
住宅手当
社宅は、会社が従業員のために住宅を借りて提供する仕組みで、その家賃を福利厚生費として経費に計上することが可能です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
福利厚生費として認められる条件
- 従業員の負担割合
従業員が賃貸料相当額の半分以上を負担する必要があります。
例:賃貸料相当額が月8万円の場合、従業員が5万円以上を負担すれば、残りの3万円を福利厚生費として計上可能です。 - 賃貸料相当額の計算方法
「賃貸料相当額」は不動産屋が提示する一般的な家賃とは異なり、以下の計算式で求められます
- 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 × 建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3(㎡)
- 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
これらを合計した金額が賃貸料相当額です。
認められないケース
- 無償貸与
社宅を無償で貸し出す場合、福利厚生費として計上できません。また、全額が給与とみなされるため、従業員の税負担が増えます。 - 現金支給の住宅手当
従業員に現金を支給し、物件選びや契約を任せる「住宅手当」は給与扱いとなり、福利厚生費として計上できません。
参照:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
食事補助
食事の補助を行う場合、社員食堂や仕出し弁当などを利用し、従業員が食事代の半額以上を負担する形であれば、福利厚生と認められやすくなります。また、企業側の負担額が一人当たり月額3,500円以下でなければなりません。
食事の現物支給が難しい場合は、食事専用チケットを支給する方法もあります。この場合も、上記と同じ条件を満たせば、福利厚生として認められます。深夜勤務のように現物支給が難しいときは、税抜300円までの現金支給であれば非課税として認められます。
福利厚生費の仕訳について
福利厚生費は、従業員の生活や働きやすさをサポートするための費用で、会社が経費として計上できます。以下では、具体的な事例を基に、福利厚生費の仕訳方法について簡単に解説します。
1. 社会保険料を負担した場合
会社が従業員の健康保険や厚生年金の会社負担分を支払った場合の仕訳例
- 健康保険料:20,000円
- 厚生年金保険料:30,000円
- 合計:50,000円
仕訳例
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預かり金 | 25,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
| 法定福利費 | 25,000円 |
ポイント
- 従業員の給与から控除した部分は「預かり金」で処理します。
- 会社負担分は「法定福利費」として計上します。
2. 全従業員を対象とした社員旅行の費用を支払った場合
慰安目的で、2泊3日の社員旅行を実施し、費用が50万円かかった場合。
仕訳例
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 500,000円 | 普通預金 | 500,000円 |
3. 全従業員を対象とした健康診断の費用を支払った場合
全従業員(30名)の健康診断を実施し、病院に45万円を支払った場合。
仕訳例
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 450,000円 | 普通預金 | 450,000円 |
福利厚生費の注意点
- 「交際費」との区別
- 従業員向けの費用は福利厚生費。
- 社外関係者への接待費用などは「交際費」として処理します。
- 給与として課税される場合
- 一部の従業員だけを対象とした支出。
- 金額が常識を超える場合。
- 現金で支給した場合など。
- 個人事業主の場合
- 従業員がいる場合にのみ福利厚生費を計上可能。
- 家族専従者だけの場合は計上不可。
その経費、雑費じゃもったいない!
正しく“福利厚生費”にできるおすすめサービス7選
福利厚生費をうまく活用することで、従業員満足度の向上や離職率の低下を実現できます。ただし、自社で福利厚生を整備するのが難しい場合、代行サービスを利用するのも一つの選択です。ここでは、多様なニーズに応えるおすすめの福利厚生代行サービスを3つご紹介します。
1.オフィスおかん|置くだけ簡単!
オフィスおかんとは「置き型社食®」を商標登録している株式会社OKANの福利厚生サービスです。導入に必要なものは、設置スペースと電子レンジのみで、手軽に社食を導入する事ができます。コンビニや弁当屋さんよりも手軽に食事がとれて、従業員は24時間いつでも“手軽でおいしい”と“栄養バランス”が両立した食事を摂りやすいことが特徴です。
| メリット・特徴 | 1. 24時間いつでも利用できる 2. 1食100円(税込)で利用できる(※1) 3. 管理栄養士が監修(※2) |
| 費用 | 初期費用:当サイト経由でお申込みいただければ初期費用0円 おかん便50:43,100円/月~ 月間納品数:50個/月~ |
※1 1品100円(税込)は想定利用価格です。
※2 レシピ等の内容や商品の選定の監督・指示を行うこと
詳しくはこちらの記事をご覧ください!





私も食べてますが、本当に美味しいです!
2.びすめし|全国の飲食店を社員食堂に
企業が従業員に昼食補助を支給し、全国の加盟飲食店を社員食堂のように利用できる福利厚生サービス。例えば1,000円チケットを5枚支給することで、毎回の食事を50%OFFで利用できます。 企業は支給額を自由に設定でき、従業員の食費負担を軽減しながら健康経営を推進できるのもうれしいポイント
| サービスの概要 | 1.会社は従業員に毎月いくら昼食代を支給するか決め、2.従業員は全国各地のびずめし加盟店を社員食堂にできる -利用イメージ- 1000円チケットを5枚配付 毎回の食事を50%OFFで利用可能など |
| メリット・特徴 | ・毎回の食事を50%OFFで利用可能 ・常設型の社員食堂に比べ、初期投資 ・電子チケット方式で導入・運用がスムーズ ・全国の加盟飲食店を社員食堂のように利用可能 |
| 費用 | 要お問い合わせ |
詳しくは:社食サービス「びずめし」| ニューノーマル時代の福利厚生↗



都心で働く社員と地方支社で働く社員のランチ格差を解消!
3.チケットレストラン|ランチが実質半額に!
チケットレストランは、全国25万店以上の飲食店やコンビニで利用できる食の福利厚生サービスです。従業員の食事補助を目的としており、スマホアプリで簡単に利用・導入が可能です。
| メリット・特徴 | 1.従業員は 非課税で食事補助を受けることができる 2.チャージ制で利用可能 3.食事代が実質半額になる |
| 費用 | 1ヶ月あたりのチャージ金額7000円/月・人(会社負担額は半額の3500円/月・人) |
詳しくはこちら:食の福利厚生-チケットレストラン



25万店以上の飲食店が実質半額に!
4.OFFICE DE YASAI|こだわりのお惣菜など約140品の多彩なメニューを100円~
オフィスに冷蔵庫(冷凍庫)を設置し、新鮮なサラダやフルーツ、こだわりのお惣菜など約140品の多彩なメニューを1つ100円から購入できる社食サービスです。ランチや間食など幅広いシーンで活用できます。新鮮なサラダやフルーツを楽しめる冷蔵プランと、日持ちが良く満足感の高い冷凍プランで、さまざまな食のニーズに対応しています。
| メリット・特徴 | 1. 大企業から中小企業まで、全国約500万人の従業員が利用している 2. 地産地消やサステナビリティを意識したサービス 3. お惣菜だけではなく、サラダやカットフルーツも選べる |
| 費用 | 要お問い合わせ |
詳しくはこちら:100円で食べられる設置型健康社食®



100円でサラダやフルーツが食べられるのは嬉しい!
5.Perk(パーク)|一人ひとりに挑むチカラを↗
Perkは、グルメ、映画、スキルアップ、レジャーなど幅広いジャンルのサービスを従業員・家族が法人優待価格で利用できる福利厚生サービスです。
1,000以上のサービスが利用可能で、ビジネススキルの向上からプライベートの充実まで幅広く従業員の多様なニーズに対応しています。簡単に導入でき、コストを抑えながら福利厚生を充実させられるため、50名~100名規模の会社に人気です。
| メリット・特徴 | 1. 1ヶ月あたりの利用サービス件数上限なし 2. 面倒な手続きが不要 3. 導入費用の負担ゼロ |
| ミニマムプラン費用 | 初期費用:0円 10名ごとの契約で一人当たり、280円~1250円/月※ 10人:一人当たり、1250円/月 50人:一人当たり、400円/月 100人〜:一人当たり、280〜400円/月 |
| 利用促進プラン費用 | 100人(月500P含む):一人当たり、975円/月 |
※プランはすべて12ヶ月契約となっています。
詳しくはこちらPerk(パーク)- 一人ひとりに挑むチカラを↗



コンビニやカラオケ、飲食チェーン、映画館など、社員が使いやすい福利厚生になっています!
6.SELECTS for Business|法人向けカタログギフトサービス
SELECTS for Businessは、法人向けカタログギフトサービスで、福利厚生や社員エンゲージメント形成に活用できます。オンラインショップの商品を自由に掲載でき、受け取り方法も多様です。独自のカタログを作成することができます。
| メリット・特徴 | 1. プレゼントキャンペーンや成約特典としても利用できる 2. 自社製品を社員に使ってもらうきっかけになる 3. 株主優待としても活用できる |
| 費用 | システム利用料 + 掲載する商品の価格 ※システム利用料 ( 有料オプションなし ) ・完全オンラインタイプ 0 円 / 個 ・プラスチックカード、メッセージカードタイプ 550 円 / 個 ・木箱入りカタログギフトタイプ 650 円 / 個 |
詳しくはこちら:オリジナルカタログギフト/ SELECTS for Business 法人ギフトにおすすめ (旧名:ギフトキッチン/ gift kitchen)↗



Amazonや楽天、Base等のECサイトの商品ならほぼ何でも掲載できる!
7.giftee for Business|謝礼をお手軽に


giftee for Businessは、デジタルギフトを提供するサービスで、企業の販促活動や福利厚生に利用できます。URLを送るだけでギフトを贈ることができ、在庫管理や個人情報の取得が不要です。工数やコストを削減し、手軽にインセンティブを提供できます。
| メリット・特徴 | 1.170以上のブランド・約1,000種類の商品ラインナップから商品選択ができる 2.未使用のポイントは繰り越し可能なため掛け捨てにならず無駄がない 3.制度の実現制度設計や導入支援、日々の運用までサポートが充実している 4.ポイントが貯まるほど交換可能なギフトが増える |
| 費用 | 商品代金(商品単価 × 数量)+発行手数料(商品代金 × 10%) |
詳しくはこちら:デジタルギフトでキャンペーンや謝礼をお手軽に giftee for Business



受け取り後にユーザーが商品を選べる「選べるギフト」も利用可能!
まとめ|福利厚生は適切な運用で節税のメリットが得られる
福利厚生費について、計上するための要件や、注意すべきポイントについて解説しました。
福利厚生は従業員の満足度を高めるだけでなく、適切に運用することで企業は節税のメリットを得られます。しかし、福利厚生は必ずしも全てが節税になるわけではありません。
「福利厚生費」として計上するためには、3つの条件を満たす必要があります。
- 全従業員に対して公平に適用されていること
- 社会通念上妥当な金額であること
- 現金支給ではないこと
家賃補助や交通費補助は、多くの企業が提供する人気の福利厚生ですが、これらを「福利厚生費」として経費に計上するには、一定の条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合、課税対象となるため注意が必要です。
しかし、「どの福利厚生が節税の対象になるのか」「自社に最適な制度は何か」と悩む企業も多いのではないでしょうか?
そんな方は、ぜひ弊社の無料コンシェルジュサービスをご活用ください!
現在、先着50社限定で、専門アドバイザーが企業の状況やニーズに合わせた最適な福利厚生導入プランをご提案いたします。
無料コンシェルジュサービスを活用してより効果的な福利厚生制度を作っていきましょう!