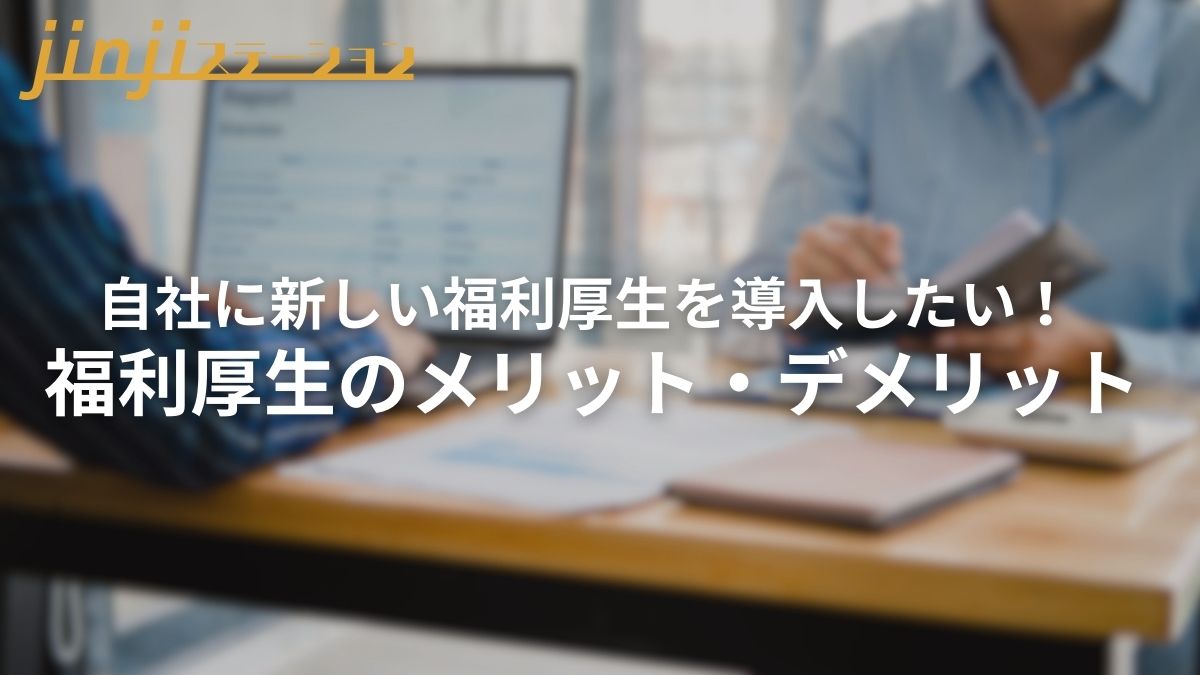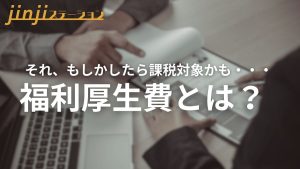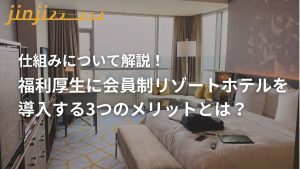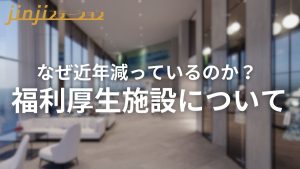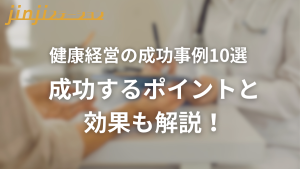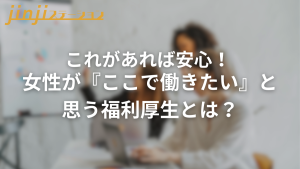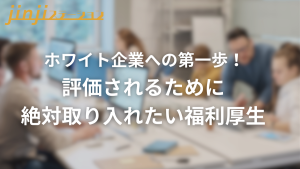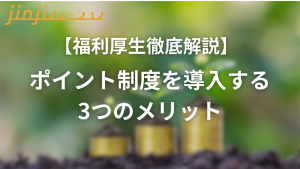従業員を満足させられているかわからない・・・
福利厚生を導入したいけど、何から始めたらいいのかわからない・・・
そんな疑問を感じたことはありませんか?
今、給与だけでなく福利厚生の充実度を重視する求職者が増えています。新卒・中途採用でも、どんな福利厚生を用意しているかが企業の魅力を左右する時代。とはいえ、どんな制度を導入すればいいのか迷う企業も多いのが現状です。
そこで、この記事では、従業員満足度を高める福利厚生の仕組みや、新しい制度を導入するメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
ぜひこの記事を読んで、改めて福利厚生のあり方を見直してみませんか?
企業が福利厚生を導入する目的とは?
福利厚生は、単なる”おまけ”や”付加価値”ではありません。企業が従業員とその家族を支え、働きやすい環境を提供するための大切な仕組みです。
企業が福利厚生を導入する目的は、大きく以下の3つに分けられます。
1.優秀な人材を採用するため
日本では、かつて「終身雇用」が当たり前とされていましたが、経済の長期低迷により、その仕組みは崩れつつあります。そのため、求職者が企業を選ぶ基準も変化し、給与だけでなく福利厚生の充実度が重視されるようになりました。企業は、福利厚生を整えることで、求職者に「この会社なら安心して働けそうだ」と思ってもらい、優秀な人材に選ばれるための大きなアピールポイントとしています。
2.従業員の定着率を向上させるため
人手不足が深刻化している現在、自社で育てた人材が辞めてしまうことは、業績低下につながるリスクがあります。福利厚生を充実させることで、従業員の辞める理由を減らすことができます。従業員が長く働き続けることで、職場の安定と企業全体の生産性を保つことができます。
3.職場環境を改善し、企業イメージを向上させるため
従業員が働きやすい環境を整えることは、企業にとって多くのメリットをもたらします。育児支援や健康サポート、リモートワーク制度などの導入は、従業員のストレスを減らし、モチベーションを高めるだけでなく、企業全体のパフォーマンス向上にも直結します。
さらに、こうした職場環境の整備は、企業の社会的評価を高める大きなポイントにもなります。「従業員を大切にする会社」というイメージは、求職者や顧客にも好印象を与え、企業のブランド力を強化します。結果として、優秀な人材の採用や取引の拡大につながり、競争力のある企業として成長を後押しする大きな要因となるのです。



今や福利厚生は”コスト”ではなく、”投資”です!
法定福利厚生と法定外福利厚生について
企業における福利厚生は、大きく分けて「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分類されます。これらの違いを理解することは、従業員が自身の権利や利用可能な制度を把握する上で非常に重要です。
法定福利厚生とは
法定福利厚生とは、企業が従業員に対して必ず提供しなければならない福利厚生です。これは法律で定められており、企業は従業員の働きやすさや生活の安定をサポートするための制度です。以下の6つ法定福利として定められています。
1. 健康保険
病気やケガで病院に行ったときに、医療費の自己負担が3割になる制度です。会社に勤めている人は「健康保険(社会保険)」に加入し、会社が保険料の半分を負担してくれます。さらに、扶養家族(配偶者や子ども)は追加の保険料なしで保険が適用されるのが特徴です。
健康保険のポイント
- 自己負担は3割(医療費の70%を保険が負担)
- 扶養家族も対象(配偶者や子どももカバーされる)
- 傷病手当金(病気やけがで働けないときの補助)や 出産手当金(出産時の支援)などの給付あり
2. 厚生年金保険
将来の年金をもらうための制度です。会社に勤めている人は「厚生年金」に加入し、保険料は会社が半分負担してくれます。会社員が受け取る年金制度で、 国民年金の上乗せ として機能します。
厚生年金のポイント
- 老後にもらえる年金額が増える(国民年金+厚生年金)
- 障害年金や遺族年金 も受け取れる(事故や病気、家族の生活を守る)
- 企業と従業員が保険料を半分ずつ負担
3. 介護保険
40歳以上になると、介護が必要になったとき、介護サービスの費用を軽減するための制度です。会社に勤めている人は、給与から自動で介護保険料が引かれるため、特に手続きは必要ありません。
介護保険のポイント
- 40歳以上 から保険料を支払う
- 介護が必要になったとき、介護サービス費用の一部を負担(自己負担は1割~3割)
- 要介護認定を受けると、訪問介護や施設入所などの支援が受けられる
4. 労災保険
仕事中や通勤中のケガや病気の医療費が100%補償されます。さらに、治療で働けない期間も給料の約80%が支給されるので、安心して療養できます。保険料は全額会社負担のため、従業員の負担はありません。
労災保険のポイント
- 医療費は全額補償(自己負担なし)
- 休業補償(働けない間の収入を補助)
- 障害や死亡時の補償 もあり(家族への支援も含む)
5. 雇用保険
雇用保険は、 従業員が仕事を失ったときや、育児・介護などで一時的に働けないとき に生活を支えるための 公的な保険制度 です。企業で働く人は基本的に 全員が加入対象 で、会社と従業員が保険料を負担します。
雇用保険のポイント
- 失業手当(基本手当) がもらえる(再就職までの支援)
- 育児休業給付 で、育休中の収入を補助
- 職業訓練や就職支援サービス も充実
6.子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金とは、 企業が負担する育児支援のための資金 で、保育園の整備や子育て支援に活用される制度です。これは すべての企業が負担 し、従業員の給与からは引かれません。つまり、従業員の負担はゼロ で、企業側だけが拠出する形になっています。
子ども・子育て拠出金のポイント
- 企業が全額負担(従業員の負担なし)
- 保育園や幼児教育の支援に活用
これらの制度は、企業規模や業種に関わらず、すべての企業が従業員に提供しなければなりません。
法定外福利厚生とは
法定外福利厚生とは、企業が従業員に対して独自に提供する福利厚生のことです。法律で義務づけられているわけではなく、企業が「社員の働きやすさをサポートするために用意している制度」です。そのため、内容は会社ごとに大きく異なります。
法定外福利厚生が充実している企業は、社員の満足度が高くなりやすいため、企業の魅力を高めるためにも導入されることが多いです。主な法定外福利厚生には以下のようなものがあります。
1. 住宅手当
住宅手当・家賃補助とは、会社が従業員の住居費用の一部を負担し、経済的な負担を軽減するための制度です。特に都市部では家賃が高額になりがちであり、住居費が生活費の大部分を占めることも少なくありません。そのため、住宅手当のある企業に勤めることで、毎月の支出を抑えながら生活を送ることができます。
住宅手当・家賃補助のポイント
- 会社が毎月の家賃の一部を負担するため、生活費の節約につながる
- 企業が借り上げた物件(社宅)に住むことで、通常の賃貸よりも安く住める
2. 通勤手当
交通費支給とは、通勤にかかる交通費(電車・バス・車などの移動費)を会社が補助する制度であり、特に公共交通機関を利用する人にとっては大きなメリットとなります。企業によっては、定期券代を全額負担するケースや、一定額まで支給するケース、さらには車通勤の場合にガソリン代や駐車場代を補助する場合など、支給の形はさまざまです。
交通費支給のポイント
- 公共交通機関を利用する場合、定期券代の全額または一部を負担してもらえる
- マイカー通勤が認められている企業では、ガソリン代や駐車場代が補助されることがある
- 交通費の上限が決められている場合もあり、企業ごとに支給ルールが異なる
3. 社員食堂
食事補助とは、社員の食費負担を軽減するために、会社が食事の費用を補助する制度です。会社によっては社員食堂を設けて格安で食事を提供するケースや、コンビニやレストランで使える食事クーポンを支給するケースもあります。特に、昼食代は毎日のことなので、会社の補助があると大きな節約につながります。
食事補助のポイント
- 社員食堂がある場合は、安くて栄養バランスの良い食事をとることができる
- 提携しているコンビニやレストランで利用できる食事クーポンを配布する企業もある
- 毎月決まった額を食費補助として支給するケースもあり、食費の負担を軽減できる
4. フレックスタイム制度
資格取得支援とは、社員のスキルアップを目的として、資格取得の費用を企業が補助する制度です。業務に直結する資格だけでなく、語学やITスキル向上のための資格にも適用されることがあり、キャリアアップを目指す人にとって非常に役立つ制度です。
資格取得支援のポイント
- 受験料や教材費を全額または一部補助し、資格取得をサポートする
- 社内で研修を実施し、資格取得のための勉強環境を整える企業もある
5. 在宅勤務制度
在宅勤務制度とは、オフィスに出社せずに自宅で業務を行うことを許可する制度で、特にIT業界や事務職を中心に普及が進んでいます。近年ではテレワークの需要が増加し、多くの企業が導入するようになりました。企業によっては、在宅勤務に必要なPCやWi-Fi環境の整備を支援する補助金を提供するケースもあります。
在宅勤務制度のポイント
- オフィスに出社せずに、自宅やカフェなど自由な場所で働ける
- 必要な機材(PC・モニター・Wi-Fiなど)を会社が支給または補助する
- フルリモート(完全在宅勤務)や、週に数回のリモート勤務など、柔軟な運用が可能
6. 育児・介護支援
育児・介護支援制度とは、従業員が子育てや家族の介護をしながら働き続けられるようにサポートする制度で、特に共働き世帯や介護を必要とする家庭にとって重要な福利厚生です。企業内に保育所を設置したり、育児休業の期間を法定基準より長く設定するなど、柔軟な働き方を支援する企業が増えています。
育児・介護支援のポイント
- 企業内に保育施設を設置し、安心して働ける環境を提供する
- 育児休業・介護休業の期間を延長し、ライフステージに応じた働き方を支援
- 介護休暇や介護施設の利用補助金を支給し、介護負担を軽減
7. 資格取得支援
資格取得支援とは、社員のスキルアップを目的に、業務に関連する資格の受験費用や学習費用を企業が補助する制度です。特に、IT・金融・製造業など専門性の高い業界では、社員のスキル向上が企業の成長にも直結するため、積極的に導入されています。
資格取得支援のポイント
- 受験料や教材費を全額または一部補助し、資格取得をサポートする
- 合格者には報奨金を支給し、スキルアップのモチベーションを高める
- 社内で研修を実施し、資格取得のための勉強環境を提供する
8. 社内研修制度
社内研修制度とは、企業が従業員向けに研修プログラムを提供し、スキル向上やキャリアアップを支援する制度です。入社時の新人研修だけでなく、管理職向け研修や専門スキルの習得を目的とした研修もあります。
社内研修制度のポイント
- 社内講師や外部講師による研修があり、学習機会が豊富
- 管理職向けのリーダーシップ研修など、キャリアアップ支援も充実
9. 従業員持株制度
従業員持株制度とは、社員が自社の株を購入できるようにする制度で、長期的な資産形成を支援する仕組みです。企業によっては、社員の株購入時に補助金を出す場合もあります。
従業員持株制度のポイント
- 会社の業績向上が個人の資産増加にもつながる
- 株購入時に企業が一定額を補助するケースもある
- 長期的な資産形成を目的とした福利厚生の一つ
10. リフレッシュ休暇
リフレッシュ休暇とは、一定の勤続年数を超えた社員に対して特別に付与される長期休暇のことです。リフレッシュ休暇を取得しやすくするために、企業が特別手当や旅行補助金を支給するケースもあり、単なる休暇ではなく「有意義な時間を過ごしてもらうこと」を目的とした福利厚生として活用されています。
リフレッシュ休暇のポイント
- 長期勤続者が取得できる特別休暇制度
- 休暇中の旅行費用を会社が一部補助する
- 特別手当を支給するケースもある
このように法定福利厚生は、すべての従業員に共通して適用されますが、法定外福利厚生は会社が自由に決めることができます。多くの企業は、社員の希望や会社の方針に合わせて、独自の制度を作っています。
特に、転職が活発な業界では他社との差を生む重要なポイントとなります。例えば、リモートワークや社員割引制度、住宅補助など、企業がどのような制度を導入するかによって、企業を魅力的に感じるかに大きな影響を与えます。
また、企業が法定外福利厚生を導入する際には、従業員のニーズをしっかり把握し、業界の動向を踏まえた上で時代に合った制度にすることも重要です。
法定福利厚生とのバランスを考えながら、長期的な企業の成長や社員のモチベーション向上アップを目指しましょう!
福利厚生の従業員の自己負担額の目安
福利厚生制度は、従業員に多くのメリットをもたらす一方で、自己負担は完全になし!というわけではありません。多くの場合、従業員にも一定の自己負担が発生します。ここでは、主要な福利厚生制度における従業員の自己負担額を比較し、各制度を活用する際の注意点について詳しく見ていきましょう。
法定福利厚生
| 健康保険 | 標準報酬月額の約5% |
| 厚生年金 | 標準報酬月額の約9% |
| 雇用保険 | 給与の約0.3% |
| 労災保険 | 業種により異なる |
法定外福利厚生
| 住宅手当 | 1-5万円 |
| 通勤手当 | 実費(上限あり) |
| 食事補助 | 0.5-1万円 |
| 健康診断 | 企業が全額負担することが多い |
| 育児・介護支援 | 必要に応じて(数万円) |
| 自己啓発支援 | 1-5万円 |
| 従業員持株制度 | 任意(数千円〜数万円) |
| 財形貯蓄 | 任意(数千円〜数万円) |
注意点
- 実際のコストは企業や個人の状況により大きく異なる場合があります。
- 法定外福利厚生は企業によって提供内容や自己負担率が異なります。
- 一部の福利厚生は利用頻度や条件によってコストが変動します。
- 在宅勤務の増加により、一部の福利厚生の利用状況や提供方法が変化する可能性があります。
- 税制上の取り扱いについては、個別に確認が必要です。
福利厚生制度は、従業員の生活をサポートし、企業の魅力を高める大切な要素です。しかし、各制度には一定の自己負担が発生するため、「どの福利厚生をどの程度の負担で提供するのが最適か」を検討することが求められます。
従業員のニーズや企業のコストバランスを考慮し、負担感を抑えつつ、満足度の高い福利厚生を設計することが大切です。適切な制度設計によって、従業員の定着率向上や採用競争力の強化にもつながるでしょう。
企業が新しい福利厚生を導入する5つのメリットとは?
福利厚生の導入は、従業員だけでなく企業にとっても多くのメリットをもたらします。企業が福利厚生を導入することで、以下のようなメリットが得られます。
- 優秀な人材を採用できる!
- 従業員が長く働き続けてくれる
- 従業員のやる気と効率がアップする
- 会社の評判が良くなる
- 節税につながる
1.優秀な人材を採用できる!
福利厚生が充実している会社があると「この会社で働きたい!」と誰もが感じますよね。例えば、家賃補助や通勤手当があれば生活が楽になり、リモートワーク制度があると働き方の自由度が上がります。こうした制度は特に若い世代や中途採用の人にとって魅力的です。
2.従業員が長く働き続けてくれる
働きやすい環境があると、従業員は「この会社でずっと働きたい」と思うようになります。例えば、育児や介護を支援する制度があれば、生活に困ったときも安心して働き続けることができます。その結果、会社全体の離職率が下がります。
3.従業員のやる気と効率がアップする
従業員が健康で快適に働ける環境が整うと、仕事に集中しやすくなります。たとえば、社員食堂やスポーツクラブの利用補助を提供すれば、心も体も元気な状態を保てます。そうすることで、会社全体の仕事の効率が上がります。
4.会社の評判が良くなる
福利厚生が整っていると、「従業員を大切にする会社」として社会から評価されます。この良いイメージは、取引先やお客様、そして求職者にも好印象を与え、会社の信用度やブランド力を高めることにつながります。
5.節税につながる
福利厚生に使った費用は、「福利厚生費」として経費に計上できる場合があります。これにより会社の税金が軽減されるので、財務面でのメリットも期待できます。
【デメリット】福利厚生を導入するにあたって、知っておくべき落とし穴とは?
福利厚生制度は従業員の生活を支援する一方で、見過ごされがちなデメリットも存在します。充実した制度が思わぬ落とし穴となる可能性もあるため、その光と影を理解することが重要です。ここでは、福利厚生のデメリットについてご紹介します。
- コストがかかる
- 運用が手間になる
- 全員に平等な満足感を与えるのが難しい
- 効果がすぐに見えない場合がある
- 廃止すると不満が出る可能性がある
1.コストがかかる
福利厚生を充実させるには、それなりの費用が必要です。例えば、健康保険や住宅手当、育児支援などを用意すると、1人あたり月に数万円以上のコストがかかることがあります。この費用をどうやってカバーするかが課題になります。
対策: コストを抑えるために助成金を活用したり、外部の福利厚生サービスを利用することで費用対効果を最大化できます。
2.運用が手間になる
福利厚生を実施するには、制度を管理する人手が必要です。例えば、従業員がどの制度をどのくらい利用しているのか確認したり、新しい制度を追加したりする作業が発生します。この運用を効率化する工夫が求められます。
対策: 管理業務を簡略化するために、専用のソフトウェアや代行サービスを導入することで、効率化を図れます。
3.全員に平等な満足感を与えるのが難しい
福利厚生は、従業員全員が同じように活用できるわけではありません。もし新しい福利厚生が従業員のニーズに合わなければ、利用されないどころか「無駄な制度」と思われてしまうリスクがあります。
対策: 「カフェテリアプラン」のように、従業員が自分に合った制度を選べる仕組みを導入することで、不公平感を軽減できます。
4.効果がすぐに見えない場合がある
福利厚生の多くは、長期的な視点での効果が期待されます。従業員が喜んでいるかどうかや、仕事がよりうまくいくようになったかどうかは、すぐには目に見えません。
そのため、導入してすぐに成果が出ない場合、経営陣にとって費用対効果がわかりにくいことがあります。
対策: 導入時に目標を設定し、定期的に利用状況や効果を分析して、改善ポイントを明確にする
5.廃止すると不満が出る可能性がある
一度導入した福利厚生を廃止する場合、従業員から反発が出ることがあります。特に、家賃補助や保険など、生活の一部となっている制度を急に無くすと、従業員の不満が高まり、信頼を損なうリスクがあります。
対策: 廃止や変更を行う際は、十分な説明を行い、代替案を用意することで、従業員の納得を得る努力をする
新しく福利厚生制度を導入する手順とは?失敗しないための7つのステップ
新たな福利厚生制度を導入する際には、慎重な計画と実行が不可欠です。以下に、成功のための重要なステップと注意点をまとめます。
新しい福利厚生制度を導入する7つのステップ
1. 従業員の希望を聞いて、会社の目標を決める
まず、従業員の本当の希望を知ることから始めましょう。アンケートを実施したり、直接対話の機会を設けたりして、従業員が求めているものを正確に把握します。同時に、会社が大切にしている価値観や、どのような人材を求めているかを考慮し、新しい制度の目的を明確に定めます。これにより、従業員のニーズと会社の方針が合致した、意義のある制度を作ることができます。
2. 制度の中身を考える
次に、具体的な制度の内容を検討します。この段階で重要なのは、法律に違反していないかを慎重に確認することです。不明な点があれば、労務専門家や弁護士などの専門家に相談しましょう。また、将来の状況変化に対応できるよう、柔軟性のある仕組みを心がけることも大切です。
3. お金の計算をして、予算を確保する
制度の実現可能性を判断するため、詳細な費用計算を行います。初期投資だけでなく、毎年継続的にかかる運用費用も細かく算出します。そして、この新しい制度を会社の長期的な財政計画に組み込みます。これにより、一時的なものではなく、持続可能な制度として確立することができます。
4. 導入の計画を立てる
制度の全面的な導入を一気に行うのではなく、段階的な導入計画を立てます。具体的なタイムラインを作成し、各段階で何をするか、誰が担当するかを明確に定めましょう。
5. 従業員への説明を考える
新しい制度について、従業員にわかりやすく説明する方法を考えます。説明会を開いたり、詳しい資料を配布したり、社内のネットワークで情報を公開したり、さまざまな方法を使って伝えましょう。また、従業員からの質問や不安に対応する窓口も用意します。こうすることで、制度への理解を深めて、スムーズに導入できるようにします。
6. 小さく始めて、意見を聞く
本格導入の前に、まずは小規模で試し運用を行います。少人数のチームで新しい制度を試し、問題や改善点を見つけてる期間をつくることで、参加者からの意見を積極的に集められます。そのため制度の改善に反映する際に、実際に大規模に導入するときのリスクを抑え、より効果的な制度に仕上げることができます。
7. 本格的に始めて、定期的に見直す
試し運用で得た知見を活かして、いよいよ本格的に導入を始めます。スムーズに進めるために、専任のサポート担当者を配置して、従業員の質問や困りごとにすぐ対応できる体制を整えます。導入後も、制度の効果や使い勝手を定期的に確認し、必要に応じて改善を重ねていきます。これにより、常にベストな状態を保つことができます。
これらのステップを丁寧に踏むことで、従業員と会社の双方にとって有益な、持続可能な福利厚生制度を構築することができるでしょう。
社員のニーズに合った福利厚生代行サービスを選ぶには?
福利厚生は、「あるだけ」ではなく、「社員にとって本当に役立つもの」を選ぶことが大切です。どんなに良い制度を導入しても、社員が活用しなければ意味がありません。ここでは、社員のニーズを把握し、最適な福利厚生を選ぶコツを紹介します。
1. 社員の意見を直接聞く
まず大切なのは、社員がどんな福利厚生を求めているのかを知ることです。以下の方法で、社員の本音を集めましょう。
アンケートを実施する
「今ある福利厚生で満足している?」「どんな制度があれば嬉しい?」といった質問を用意し、匿名で回答できるようにすると、率直な意見が集まりやすくなります。
既存の制度の利用状況を確認する
導入済みの福利厚生がどれくらい使われているかをデータで把握し、利用率が低いものは改善・見直しを検討しましょう。
2. 社員のライフスタイルや年齢層に合わせる
社員の年齢層やライフスタイルによって、求める福利厚生は大きく異なります。
若手社員が多い場合
スキルアップ支援(研修・資格取得補助)や家賃補助など、キャリア形成や生活支援系の制度が人気。
育児世代が多い場合
育児休暇の充実やベビーシッター補助、時短勤務制度など、育児との両立を支援する制度が喜ばれます。
シニア層が多い場合
健康診断・人間ドック補助、 医療費補助など、健康維持をサポートする制度が重要に。
自社の社員構成を考えながら、どの世代にとってもメリットがある制度をバランスよく導入するのがポイントです。
3.社員のニーズがバラバラなら、カフェテリアプランがおすすめ!
社員の年齢層やライフスタイルに合わせて福利厚生を選ぶのは大切ですが、社員の価値観がバラバラで「どの制度が最適かわからない」というケースも少なくありません。
若手社員・育児世代・シニア層が混在する企業では一律の福利厚生では満足度に偏りが出てしまうこともあります。
そんな時に役立つのが 「カフェテリアプラン」 です。
カフェテリアプランとは?
企業が用意した福利厚生メニューの中から、社員が自分の好きなサービスを選べる制度です。会社が決めたポイント(補助額)を付与し、社員が自由に使える仕組みになっています。
例えばこんな使い方が可能!
- 若手社員 → スキルアップ支援や家賃補助にポイントを利用
- 育児世代 → ベビーシッター補助や育児支援サービスに活用
- シニア層 → 健康診断やフィットネスジム補助を選択
カフェテリアプランの例としては、「ベネフィット・ワン」や「リロクラブ」などが挙げられます。企業ごとにカスタマイズできるプランもあるため、規模や予算に応じて柔軟に調整可能です。
社員の多様なニーズに応えながら、コストの無駄を防ぐなら、カフェテリアプランの導入が効果的な選択肢でしょう。
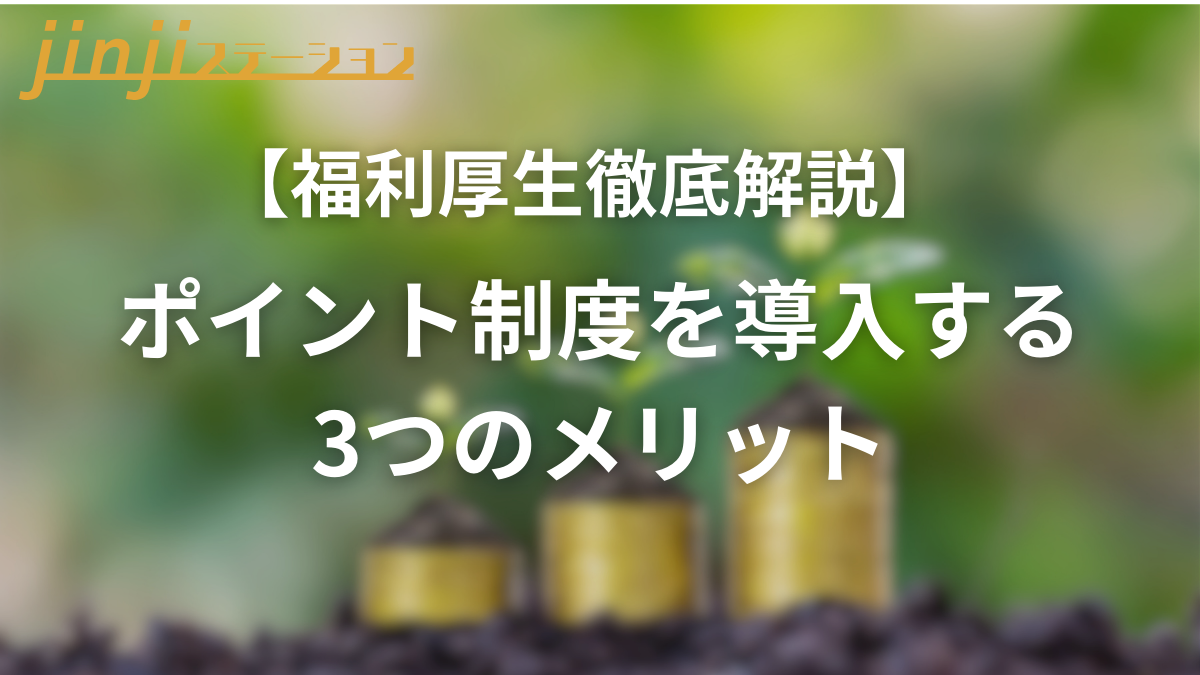
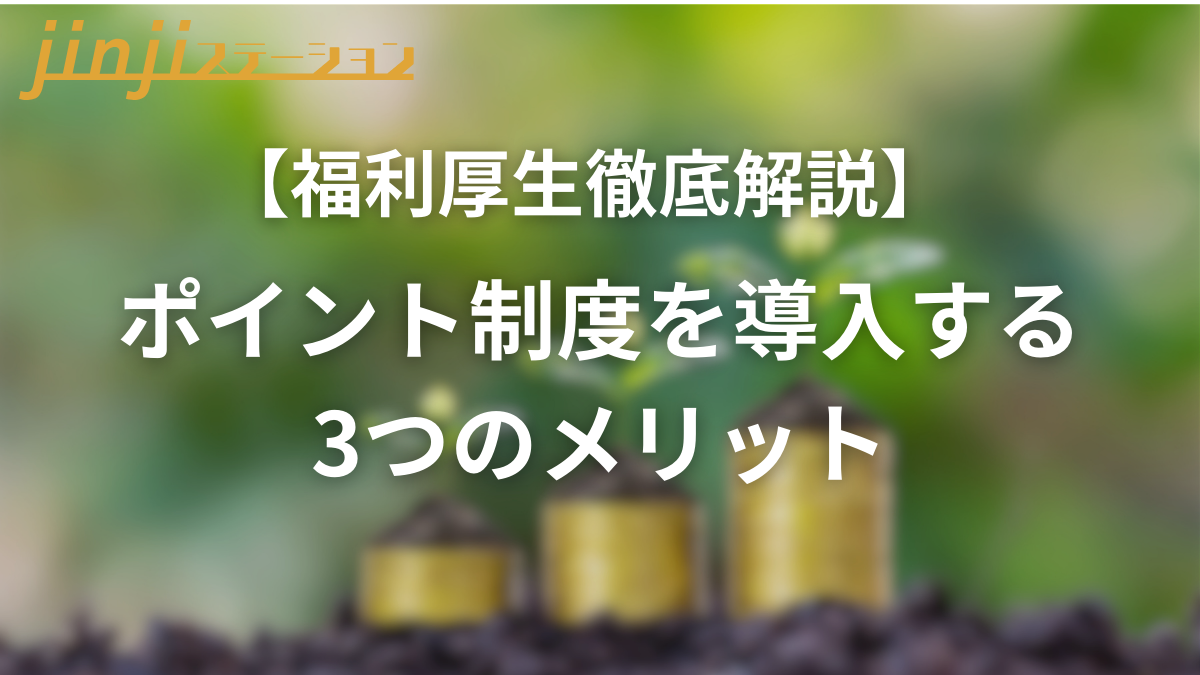
企業のユニークな福利厚生5選
Googleの「20%ルール」の実施
従業員の勤務時間の20%を自由な研究や個人プロジェクトに使える制度です。この時間から「Gmail」や「Google News」などが生まれました。
Airbnbの「旅行手当」の実施
従業員に年間2,000ドルの旅行手当を支給する制度です。自社のサービスを利用して旅行することを奨励し、従業員が製品体験を深める機会を提供しています。
サイバーエージェントの「社内結婚制度」の実施
社内恋愛を積極的に応援し、社内カップルの結婚を祝福する制度です。結婚祝い金の支給や、社内での祝賀会開催などの特典があります。
NetflixのUnlimited Vacation Policyの実施
休暇の日数制限を設けず、従業員が自由に休暇を取得できる制度です。従業員の自主性を尊重し、ワークライフバランスの向上を図っています。
Patagonia社の「Let My People Go Surfing」の実施
従業員がサーフィンや他のアウトドア活動に参加するために、勤務時間中でも自由に外出できる制度です。会社の環境保護の理念と一致しています。
ユニークな福利厚生についてもっと知りたい方はコチラ!


まとめ
福利厚生は、会社が従業員の働きやすさや生活をサポートするために用意する大事な仕組みです。福利厚生が充実していると、優秀な人を採用しやすくなり、今いる従業員も安心して長く働けるようになります。また、従業員が元気に仕事をできる環境を整えることで、会社全体の仕事の効率が上がり、良い評判にもつながります。
ただし、福利厚生にはお金がかかったり、全員が満足できる制度を作るのが難しかったりと、課題もあります。これらの問題を解決するためには、従業員の意見を聞いたり、助成金を使ったり、みんなが好きなものを選べる仕組みを取り入れることが大切です。
新しい福利厚生を始めるときは、小さい規模で試してから本格的に導入すると、失敗を減らせます。福利厚生は、会社と従業員が一緒に成長していくための大切な取り組みです。この機会に、会社でどんな制度が必要か考えてみましょう!