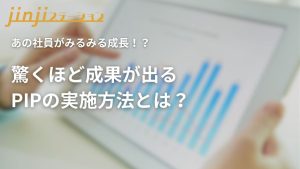近年、アサーティブ・コミュニケーションが多くの企業で注目を集めています。このスキルがあれば、自分の考えをしっかり伝えつつ、相手の意見もきちんと受け止め、前向きな話し合いができるようになります。
特に、多様な価値観が共存する現代の職場では、アサーティブ・コミュニケーションは誰もが納得できる話し合いを実現するための鍵として注目されています。そこで
- 「どうすれば社員同士がスムーズに意見を共有できるのか?」
- 「職場の誤解やトラブルを減らして、働きやすい環境を作りたい!」
そんなあなたに、この記事では、アサーティブ・コミュニケーションについて、重要視されている背景やメリット、よくある間違ったコミュニケーションや実際に使えるテクニックについて解説します。
社員のモチベーション向上や離職率の低下にもつながる内容なので、ぜひ、この記事を読んで今回ご紹介するテクニックを職場で試してみてください!

不満や意見を直接伝えず、間接的に表現してしまっていませんか?
そのコミュニケーションだと、一時的には問題を回避できても、後から大きなトラブルにつながってしまうかもしれません
アサーティブ・コミュニケーションとは?


アサーティブ・コミュニケーションとは、「自分の考えをしっかり伝えながら、相手の意見も大切にする話し方」のことです。アサーティブという言葉には、「自分の気持ちをしっかり伝える」という意味があります。
この方法を使うと、相手を傷つけたり、無理に押し付けたりすることがなく、気持ちよく話し合うことができます。そして、自分も無理をせずに意見を言えるので、ストレスを減らすことができます。
アサーティブ・コミュニケーションは、学校、家庭、友達付き合い、職場などで、意見が対立したときや頼みごとをする際に役立ちます。
なぜアサーティブ・コミュニケーションが大切なのか?
では、アサーティブ・コミュニケーションが大切とされる3つの理由をそれぞれ見てみましょう。
1. オンラインでのやりとりが増えたから
リモートワークやオンライン授業が増え、対面で話す機会が少なくなりました。そのため、相手の気持ちを理解したり、自分の考えをうまく伝えるのが以前よりも難しくなっています。
アサーティブ・コミュニケーションなら、言葉だけでも気持ちを伝えやすくなり、誤解を防ぐことができます。たとえば、チャットで「こうしてほしい」とお願いする際も、相手に配慮しながら伝えられます。
2. さまざまな文化、考え方の人と協力する時代だから
今は「多様性」がとても大切にされる時代です。異なる文化や価値観、考え方を持つ人たちと一緒に過ごす機会が増えており、学校でも職場でも、いろいろな背景を持つ人々と協力することが当たり前になってきました。
こうした環境でスムーズに話し合い、協力するためには、アサーティブコミュニケーションがとても役立ちます。
アサーティブな話し方を身につけると、自分の意見をはっきり伝えるだけでなく、相手の考えや気持ちもしっかり受け止めることができるようになります。
多様性が重視される時代だからこそ、アサーティブなコミュニケーションは、私たちが信頼関係を築きながら協力していくための大切なスキルです。
3. 問題を早く解決できるから
意見がぶつかったとき、アサーティブ・コミュニケーションを使うと問題を早く解決できます。たとえば、同僚と企画の進め方で意見が食い違う場面を想像してください。
お互い感情的になり、「自分のやり方が正しい!」と主張するだけでは、議論が平行線のまま時間だけが過ぎてしまいます。
しかし、アサーティブな話し方だと、「私はこの方法が効率的だと思っています。でも、あなたのやり方も良さそうなので、それぞれのメリットを比べてみませんか?お互いの意見を組み合わせる方法も考えたいです」と提案できます。
この話し方なら、感情的な対立を避けつつ、建設的に話を進められます。結果的に、より良い解決策が見つかり、チームの雰囲気も良くなるのがアサーティブ・コミュニケーションの強みです。
アサーティブ・コミュニケーションの3つのメリット
アサーティブな話し方は、仕事やプライベートにおいてたくさんのメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に大きな3つのメリットについて詳しく解説します。
良い人間関係が作れる
アサーティブ・コミュニケーションを使うと、自分の意見を伝えながら相手の話もきちんと聞けるので、お互いの信頼が深まります。
たとえば、職場で意見が分かれた場面を想像してください。「あなたの考えもわかります。でも、私はこういう考えを持っています」と丁寧に伝えれば、相手も「自分の意見が尊重されている」と感じ、納得しやすくなります。
さらに、相手に「この人は話していて安心できる」と思ってもらえるようになるのも大きなメリットです。結果的に、友人や家族、仕事仲間との関係が良くなり、日々の生活がより豊かになります。
ストレスが少なくなる
自分の気持ちを正直に伝えられると、心の中にたまるストレスがぐっと減り、精神的にも余裕が生まれます。
一方で、自分の意見を言えずに我慢していると、後でイライラしたり、「なんで何も言えなかったんだろう」と自己嫌悪に陥ったりすることがあります。こうした負の感情を溜め込むと、人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
アサーティブな話し方は、こうした悩みを解決する手助けになります。「相手に気を使いすぎて、自分の意見を抑えてしまう」状況から、「お互いが尊重し合いながら話し合える」関係に変わることで、心の負担が軽くなります。
話し合いがスムーズに進む
意見を出し合う場面でも、アサーティブな話し方を取り入れると話し合いがスムーズに進みます。
たとえば、チームでアイデアを出すとき、相手に「あなたはどう思いますか?」と意見を促しながら、自分の考えも「私はこう考えています」と伝えることで、自然と活発なコミュニケーションが行われます。
この方法を使えば、一方的な議論や対立を防ぎ、全員が納得できる結果を見つけやすくなります。
職場だけでなく、家庭内での話し合いでも有効です。家族それぞれの意見を聞きながら自分の希望を伝え、全員が満足する結論に近づけます。結果的に、話し合いの時間が有意義なものになり、誰もが気持ちよく感じられるでしょう。
よくある3つの間違ったコミュニケーションのタイプ
アサーティブではない話し方には、次のようなタイプがあります。
1. 攻撃的(アグレッシブ)
攻撃的な話し方は、自分の意見を強く押し通そうとするため、相手を傷つけたり、怖がらせてしまうことがあります。この話し方は、人間関係に悪影響を与える原因になりやすいです。
特徴
- 声が大きい
- 相手の話を途中で遮る
- 威圧的な言葉を使う
例
「こんな簡単なことも分からないの?」と怒鳴る。
このような話し方では、自分の意見が一時的に通ることがあっても、相手との信頼関係を壊してしまいます。相手が心を閉ざしてしまうこともあり、結果的に良いコミュニケーションができなくなります。
2. 受け身的(ノンアサーティブ)
受け身的な話し方は、自分の意見を言わずに相手に合わせる特徴があります。一見、平和に見えますが、自分が我慢をすることで心の中に不満やストレスがたまりやすくなります。
特徴
- 質問されても「どっちでもいい」と答える。
- 自分の気持ちを隠す。
例
「本当は嫌だけど、断るのが怖いから引き受ける。」
受け身的な態度は、一時的には問題を回避できても、後から大きなトラブルになることがあります。自分の気持ちを抑えることで、「本当はこう思っていた」と後悔することが多いのです。受け身でいることで相手に気を使いすぎたり、自分の意見を言わないことで誤解が生じやすくなります。
3. 作為的(パッシブアグレッシブ)
作為的な話し方は、不満や意見を直接伝えず、間接的に表現する特徴があります。この話し方は、相手に意図が伝わらないため、誤解や不信感を生む原因になります。
特徴
- 表向きは問題ないように見せる。
- 裏で不満を持ち続けたり、陰口を言う。
例
「大丈夫」と言いつつ、不機嫌な態度を取る。
作為的な態度では、相手に自分の本音が伝わらないため、状況が改善されません。また、相手は「本当に大丈夫なのだろうか?」と不安に思い、信頼関係に影響を与えます。
作為的な話し方は、人間関係をこじらせる可能性が高いため、素直に気持ちを伝えるように改善する必要があります。



作為的(パッシブアグレッシブ)はやってしまいがちですね・・・
アサーティブ・コミュニケーションの基本4つのルール
アサーティブ・コミュニケーションを実践するためには、次の4つのルールをしっかり意識することが大切です。それぞれのルールを守ることで、良い人間関係を築くことができます。
1.率直に話す
アサーティブ・コミュニケーションでは、「率直に話す」ことがとても大事です。これは、自分の考えや気持ちをわかりやすく、正直に伝えることを意味します。ただし、相手を傷つけるような言い方をしないように、丁寧で優しい言葉を使うのがポイントです。
もしあいまいな言葉を使うと、相手が誤解したり、話がうまく進まなくなることがあります。
たとえば、「どっちでもいい」と言うと相手は困ってしまいますが、「私はAがいいと思うけど、どう思う?」と言うと、相手も意見を言いやすくなります。率直に話すことで、お互いに安心して話せるようになり、良い関係が作れます。
2.対等な関係を持つ
相手と対等な立場で話すこともとても大切です。上下関係にとらわれず、お互いを尊重しながら話を進めると、自然で気持ちの良い会話ができます。相手の意見も大切にする姿勢を見せることで、相手も安心して自分の気持ちを伝えやすくなります。
たとえば、「私の考えはこうだけど、あなたの意見も聞かせてほしい」と言えば、対等な雰囲気が生まれます。こうすることで、お互いに理解が深まり、協力しやすくなります。
3.誠実に接する
嘘やごまかしを避け、相手に対して誠実に対応することも大切です。ただし、自分の意見を伝えるだけでなく、相手の話もしっかり聞きましょう。
たとえば、「あなたの提案はすごくいいと思います。でも、他の方法も一緒に考えてみませんか?」と話せば、自分の本音を伝えながら相手の気持ちも尊重できます。
誠実な態度で接すると、相手からの信頼を得やすくなり、安心して話し合える関係が作れます。
4.責任を持つ
自分の発言や行動に責任を持つことも、アサーティブ・コミュニケーションには欠かせません。自分の発言が相手にどう影響するかを考えながら話すと、より信頼感が高まります。
たとえば、「この案で進めるなら、私も最後までサポートします」と言うと、自分が責任を取る姿勢を示すことができます。こうした態度を持つことで、相手も安心して一緒に取り組めるようになり、スムーズな関係を築くことができます。
実際に使えるアサーティブ・コミュニケーションのテクニック
では、アサーティブ・コミュニケーションを日常生活で取り入れる具体的な方法について紹介します。
DESC法で伝える
DESC法は、自分の意見や感情を落ち着いて伝えるための4つのステップです。感情的にならずに話し合いたいときに、とても役立ちます。仕事でも日常生活でも使える便利なスキルなので、ぜひ試してみてください!
D(事実を伝える)
まず、相手に「状況や事実」を冷静に説明します。ここでは、自分の感情や考えを入れず、客観的な情報を伝えるのが大切です。
例:「ここ1週間、レポートの提出が予定より遅れています。」
E(感情を伝える)
次に、その事実に対して自分がどう感じているかを伝えます。感情を隠さず、でも攻撃的にならないように話すのがポイントです。
例:「このままだと全体の進行が遅れてしまうのではと心配しています。」
S(提案をする)
続いて、解決策や具体的な提案をします。相手に選択肢を与えるような伝え方が理想的です。
例:「作業の進捗を確認するミーティングを毎週行うのはどうでしょうか?」
C(次の行動を選ぶ)
最後に、次にどう行動するかを決めます。このステップがあることで、ただ意見を言うだけで終わらず、具体的な行動につなげられます。
例:「まずは、来週の火曜日からミーティングを始めるという形で進めてもいいですか?」
Iメッセージを使う
Iメッセージは、自分の気持ちや考えを「私は~」という形で伝える方法です。この話し方を使うと、相手を攻撃せずに、自分の意見をはっきり伝えることができます。
たとえば、「あなたが遅れているからダメなんだ」という言い方だと、相手を責めるように聞こえてしまい、相手が反発したり防御的になることがあります。しかし、「私はスケジュールが遅れていて心配です」という言い方なら、相手は責められているとは感じずに、自分の行動がどう影響しているのかを理解しやすくなります。
この方法では、自分の感情を正直に伝えることが大切です。ただし、相手のせいにしたり、批判的な言葉を使ったりしないように気をつけましょう。また、自分の意見を伝えたあとに「どうすればいいと思う?」と相手の意見を聞いたり、「一緒に考えたい」と提案したりすることで、よりスムーズな話し合いができます。
Iメッセージを使うと、お互いの気持ちを尊重しながら話が進むので、トラブルを防ぎやすくなります。



まずは主語を「私は〜」に徹底する習慣をつけよう!
まとめ
この記事では、アサーティブ・コミュニケーションについて、重要視されている背景やメリット、よくある間違ったコミュニケーションや実際に使えるテクニックについて解説します。
アサーティブ・コミュニケーションとは、「自分の考えをしっかり伝えながら、相手の意見も大切にする話し方」のことです。この方法を使うと、相手を傷つけたり、無理に押し付けたりすることがなく、気持ちよく話し合うことができます。
よくある3つの間違ったコミュニケーションタイプには、以下の3つのタイプがあります。
- 攻撃的(アグレッシブ)
- 受け身的(ノンアサーティブ)
- 作為的(パッシブアグレッシブ)
攻撃的な話し方は、自分の意見を押し通そうとするため、相手を傷つけたり信頼を失う原因になります。また、受け身的な話し方は、自分の意見を言わずに相手に合わせることで、不満やストレスがたまりやすくなります。
しかし、間接的な表現をしてしまう作為的な話し方では、不満を直接言わず、遠回しに表現するため、相手に誤解されることが多くなります。これらの話し方は、どれも人間関係を悪くしてしまう原因になってしまいます。
そこで、実際に使えるテクニック「DESC法」と「Iメッセージ」をご紹介しました。
DESC法では、①事実を冷静に伝え、②その状況に対する自分の感情を表現し、③解決策を提案し、④次の行動を具体的に決めることで、感情的にならずに建設的な対話ができます。
一方、Iメッセージは「私は~」という形で自分の気持ちを伝える方法で、相手を責めることなく自分の意見を分かりやすく伝えられます。これらのスキルを活用することで、相手との信頼関係を深め、問題解決をスムーズに進めることが可能になります。
アサーティブ・コミュニケーションを取り入れることで、職場の雰囲気が和らぎ、チーム全体のパフォーマンスや生産性も大きく向上します。
ぜひこの記事を読んで、実際に使えるテクニック「DESC法」や「Iメッセージ」を職場に共有してみてください!