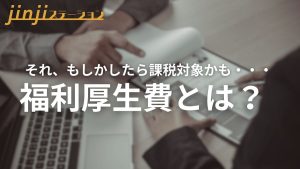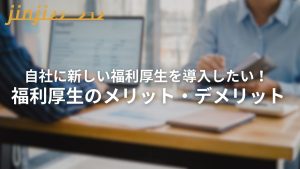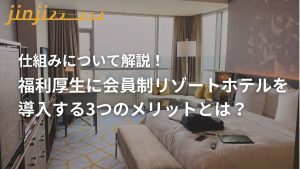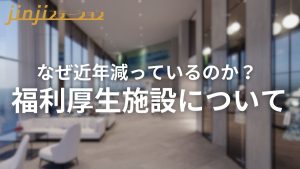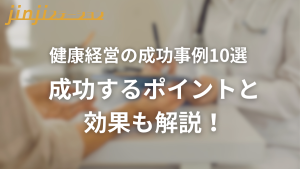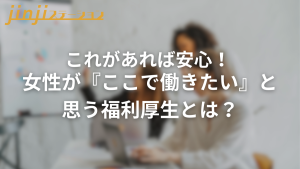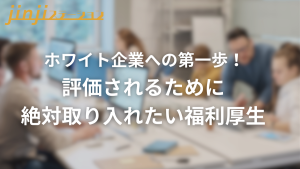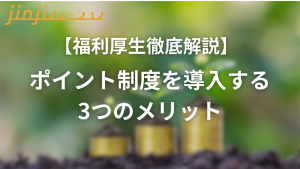近年、働き方の多様化や人材確保の競争が激しくなる中で、「福利厚生が充実している会社に入りたい」「福利厚生で社員の定着率を高めたい」といったニーズが高まっています。とはいえ、「そもそも福利厚生って何?」と気になる人も多いのではないでしょうか。
例えば、就職・転職活動中の方は「会社選びの基準として福利厚生が大事」と言われても実際にどのような制度があるのか分からないこともあるでしょう。
また、企業の人事・総務担当者や経営者にとっては、「自社の福利厚生を見直したい」「新しい制度を導入したい」と考えても、どこから手をつければよいのか迷うことも少なくありません。
あなたも、こんな悩みを抱えていませんか?
- 「福利厚生が充実している企業を選びたいけれど、どんな種類があるのか分からない…」
- 「社内制度を整えたいが、どこから始めればいいのか知りたい…」
- 「社員満足度を高めるために福利厚生を見直したいが、どんな選択肢があるのか分からない…」
こうした悩みを解決するためには、福利厚生の基本を理解しすることが重要です。
本記事では、福利厚生の種類やメリット・デメリットをはじめ、福利厚生の導入方法や代行サービスまで徹底解説します。「福利厚生について知りたい」「どんな制度を導入すればいいの?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください!

僕も就職活動の時は会社の福利厚生の充実度を気にしていました…
福利厚生とは?
福利厚生とは、企業が従業員の生活を支え、働きやすい環境を作るための制度やサービスのことです。
福利厚生には健康保険や年金など、法律で義務付けられた「法定福利厚生」と住宅手当やリフレッシュ休暇、健康支援など、企業が自由に導入できる「法定外福利厚生」があります。
特に法定外福利厚生で従業員が安心して働ける環境を整えることで、社員は仕事へのモチベーションが向上します。
また、福利厚生が充実している職場は働きやすさが向上し、優秀な人材の確保にもつながるので企業と従業員双方にとってメリットがたくさんあるのです。
特に近年では、求職者が企業を選ぶ際、給与や仕事内容だけでなく福利厚生も重要な判断基準の一つとなっています。そのため、企業が福利厚生を積極的に導入することは従業員の満足度向上だけでなく、採用競争力を高める上でも欠かせません。
福利厚生の種類
福利厚生には、法律で定められた「法定福利厚生」と、企業が独自に提供する「法定外福利厚生」の2種類があります。ここでは、その違いについて具体的に見ていきましょう。
法定福利厚生とは
法定福利厚生とは、企業が従業員に対して必ず提供しなければならない福利厚生です。これは法律で定められており、企業は従業員の働きやすさや生活の安定をサポートするための制度です。以下の6つ法定福利として定められています。
1. 健康保険
病気やケガで病院に行ったときに、医療費の自己負担が3割になる制度です。会社に勤めている人は「健康保険(社会保険)」に加入し、会社が保険料の半分を負担してくれます。さらに、扶養家族(配偶者や子ども)は追加の保険料なしで保険が適用されるのが特徴です。
健康保険のポイント
- 自己負担は3割(医療費の70%を保険が負担)
- 扶養家族も対象(配偶者や子どももカバーされる)
- 傷病手当金(病気やけがで働けないときの補助)や 出産手当金(出産時の支援)などの給付あり
2. 厚生年金保険
将来の年金をもらうための制度です。会社に勤めている人は「厚生年金」に加入し、保険料は会社が半分負担してくれます。会社員が受け取る年金制度で、 国民年金の上乗せ として機能します。
厚生年金のポイント
- 老後にもらえる年金額が増える(国民年金+厚生年金)
- 障害年金や遺族年金 も受け取れる(事故や病気、家族の生活を守る)
- 企業と従業員が保険料を半分ずつ負担
3. 介護保険
40歳以上になると、介護が必要になったとき、介護サービスの費用を軽減するための制度です。会社に勤めている人は、給与から自動で介護保険料が引かれるため、特に手続きは必要ありません。
介護保険のポイント
- 40歳以上 から保険料を支払う
- 介護が必要になったとき、介護サービス費用の一部を負担(自己負担は1割~3割)
- 要介護認定を受けると、訪問介護や施設入所などの支援が受けられる
4. 労災保険
仕事中や通勤中のケガや病気の医療費が100%補償されます。さらに、治療で働けない期間も給料の約80%が支給されるので、安心して療養できます。保険料は全額会社負担のため、従業員の負担はありません。
労災保険のポイント
- 医療費は全額補償(自己負担なし)
- 休業補償(働けない間の収入を補助)
- 障害や死亡時の補償 もあり(家族への支援も含む)
5. 雇用保険
雇用保険は、 従業員が仕事を失ったときや、育児・介護などで一時的に働けないとき に生活を支えるための 公的な保険制度 です。企業で働く人は基本的に 全員が加入対象 で、会社と従業員が保険料を負担します。
雇用保険のポイント
- 失業手当(基本手当) がもらえる(再就職までの支援)
- 育児休業給付 で、育休中の収入を補助
- 職業訓練や就職支援サービス も充実
6.子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金とは、 企業が負担する育児支援のための資金 で、保育園の整備や子育て支援に活用される制度です。これは すべての企業が負担 し、従業員の給与からは引かれません。つまり、従業員の負担はゼロ で、企業側だけが拠出する形になっています。
子ども・子育て拠出金のポイント
- 企業が全額負担(従業員の負担なし)
- 保育園や幼児教育の支援に活用
これらの制度は、企業規模や業種に関わらず、すべての企業が従業員に提供しなければなりません。
法定外福利厚生とは
法定外福利厚生とは、企業が従業員に対して独自に提供する福利厚生のことです。法律で義務づけられているわけではなく、企業が「社員の働きやすさをサポートするために用意している制度」です。そのため、内容は会社ごとに大きく異なります。
法定外福利厚生が充実している企業は、社員の満足度が高くなりやすいため、企業の魅力を高めるためにも導入されることが多いです。主な法定外福利厚生には以下のようなものがあります。
1. 住宅手当
住宅手当・家賃補助とは、会社が従業員の住居費用の一部を負担し、経済的な負担を軽減するための制度です。特に都市部では家賃が高額になりがちであり、住居費が生活費の大部分を占めることも少なくありません。そのため、住宅手当のある企業に勤めることで、毎月の支出を抑えながら生活を送ることができます。
住宅手当・家賃補助のポイント
- 会社が毎月の家賃の一部を負担するため、生活費の節約につながる
- 企業が借り上げた物件(社宅)に住むことで、通常の賃貸よりも安く住める
2. 通勤手当
交通費支給とは、通勤にかかる交通費(電車・バス・車などの移動費)を会社が補助する制度であり、特に公共交通機関を利用する人にとっては大きなメリットとなります。企業によっては、定期券代を全額負担するケースや、一定額まで支給するケース、さらには車通勤の場合にガソリン代や駐車場代を補助する場合など、支給の形はさまざまです。
交通費支給のポイント
- 公共交通機関を利用する場合、定期券代の全額または一部を負担してもらえる
- マイカー通勤が認められている企業では、ガソリン代や駐車場代が補助されることがある
- 交通費の上限が決められている場合もあり、企業ごとに支給ルールが異なる
3. 社員食堂
食事補助とは、社員の食費負担を軽減するために、会社が食事の費用を補助する制度です。会社によっては社員食堂を設けて格安で食事を提供するケースや、コンビニやレストランで使える食事クーポンを支給するケースもあります。特に、昼食代は毎日のことなので、会社の補助があると大きな節約につながります。
食事補助のポイント
- 社員食堂がある場合は、安くて栄養バランスの良い食事をとることができる
- 提携しているコンビニやレストランで利用できる食事クーポンを配布する企業もある
- 毎月決まった額を食費補助として支給するケースもあり、食費の負担を軽減できる
4. フレックスタイム制度
資格取得支援とは、社員のスキルアップを目的として、資格取得の費用を企業が補助する制度です。業務に直結する資格だけでなく、語学やITスキル向上のための資格にも適用されることがあり、キャリアアップを目指す人にとって非常に役立つ制度です。
資格取得支援のポイント
- 受験料や教材費を全額または一部補助し、資格取得をサポートする
- 社内で研修を実施し、資格取得のための勉強環境を整える企業もある
5. 在宅勤務制度
在宅勤務制度とは、オフィスに出社せずに自宅で業務を行うことを許可する制度で、特にIT業界や事務職を中心に普及が進んでいます。近年ではテレワークの需要が増加し、多くの企業が導入するようになりました。企業によっては、在宅勤務に必要なPCやWi-Fi環境の整備を支援する補助金を提供するケースもあります。
在宅勤務制度のポイント
- オフィスに出社せずに、自宅やカフェなど自由な場所で働ける
- 必要な機材(PC・モニター・Wi-Fiなど)を会社が支給または補助する
- フルリモート(完全在宅勤務)や、週に数回のリモート勤務など、柔軟な運用が可能
6. 育児・介護支援
育児・介護支援制度とは、従業員が子育てや家族の介護をしながら働き続けられるようにサポートする制度で、特に共働き世帯や介護を必要とする家庭にとって重要な福利厚生です。企業内に保育所を設置したり、育児休業の期間を法定基準より長く設定するなど、柔軟な働き方を支援する企業が増えています。
育児・介護支援のポイント
- 企業内に保育施設を設置し、安心して働ける環境を提供する
- 育児休業・介護休業の期間を延長し、ライフステージに応じた働き方を支援
- 介護休暇や介護施設の利用補助金を支給し、介護負担を軽減
7. 資格取得支援
資格取得支援とは、社員のスキルアップを目的に、業務に関連する資格の受験費用や学習費用を企業が補助する制度です。特に、IT・金融・製造業など専門性の高い業界では、社員のスキル向上が企業の成長にも直結するため、積極的に導入されています。
資格取得支援のポイント
- 受験料や教材費を全額または一部補助し、資格取得をサポートする
- 合格者には報奨金を支給し、スキルアップのモチベーションを高める
- 社内で研修を実施し、資格取得のための勉強環境を提供する
8. 社内研修制度
社内研修制度とは、企業が従業員向けに研修プログラムを提供し、スキル向上やキャリアアップを支援する制度です。入社時の新人研修だけでなく、管理職向け研修や専門スキルの習得を目的とした研修もあります。
社内研修制度のポイント
- 社内講師や外部講師による研修があり、学習機会が豊富
- 管理職向けのリーダーシップ研修など、キャリアアップ支援も充実
9. 従業員持株制度
従業員持株制度とは、社員が自社の株を購入できるようにする制度で、長期的な資産形成を支援する仕組みです。企業によっては、社員の株購入時に補助金を出す場合もあります。
従業員持株制度のポイント
- 会社の業績向上が個人の資産増加にもつながる
- 株購入時に企業が一定額を補助するケースもある
- 長期的な資産形成を目的とした福利厚生の一つ
10. リフレッシュ休暇
リフレッシュ休暇とは、一定の勤続年数を超えた社員に対して特別に付与される長期休暇のことです。リフレッシュ休暇を取得しやすくするために、企業が特別手当や旅行補助金を支給するケースもあり、単なる休暇ではなく「有意義な時間を過ごしてもらうこと」を目的とした福利厚生として活用されています。
リフレッシュ休暇のポイント
- 長期勤続者が取得できる特別休暇制度
- 休暇中の旅行費用を会社が一部補助する
- 特別手当を支給するケースもある
このように法定福利厚生は、すべての従業員に共通して適用されますが、法定外福利厚生は会社が自由に決めることができます。多くの企業は、社員の希望や会社の方針に合わせて、独自の制度を作っています。
特に、転職が活発な業界では他社との差を生む重要なポイントとなります。例えば、リモートワークや社員割引制度、住宅補助など、企業がどのような制度を導入するかによって、企業を魅力的に感じるかに大きな影響を与えます。
また、企業が法定外福利厚生を導入する際には、従業員のニーズをしっかり把握し、業界の動向を踏まえた上で時代に合った制度にすることも重要です。
法定福利厚生とのバランスを考えながら、長期的な企業の成長や社員のモチベーション向上アップを目指しましょう!
【就職・転職者向け】福利厚生が充実した会社で働くメリット
就職や転職を考える際に、「給与」や「仕事内容」だけでなく、「福利厚生の充実度」も重要なポイントになります。福利厚生がしっかりしている会社は、社員の働きやすい環境が整っておりプライベートの充実やワークライフバランスの向上にもつながります。
今回は福利厚生が充実している会社で働く3つのメリットをわかりやすく解説します。
メリット① 仕事とプライベートの両立がしやすくなる
福利厚生が充実している会社では、ワークライフバランスを保ちやすくなります。 例えば、フレックスタイム制度やリモートワーク制度が整っている企業なら、満員電車を避けた出勤が可能になったり、自宅で効率的に仕事ができることも。その結果、通勤のストレスが減り、仕事のパフォーマンス向上にもつながります。
また、育児支援制度が充実している企業では、育休を取得しやすく子育てと仕事の両立がしやすかったり、介護休暇の拡充がある会社では、家族の介護が必要になったときに安心して働き続けることができます。
メリット② 生活費を節約できる
福利厚生が充実している会社では、社員の生活をサポートするために住宅手当・家賃補助、交通費支給、食事補助などの制度が整っています。 これらの制度を利用することで、毎月の生活費を大きく節約することができます。
実際に働いてみると、給料をもらっていてもなかなか貯金ができないと感じる人は多いもの。特に都市部での一人暮らしや、外食が多くなりがちな場合、手取りがあっても余裕のある生活を送るのが難しいことも多いのです。
そのため、福利厚生を活用して固定費や日々の出費を抑えることが、無理なく貯金を増やすための大きなポイントになります。
例えば、住宅手当がある企業は、家賃の一部を会社が負担してくれるため、都市部での生活も経済的に楽になります。 また、交通費支給があれば通勤にかかる費用を抑えられ、食事補助がある企業では、社員食堂の利用やランチ代の補助を受けることができます。
メリット③キャリアアップがしやすくなる
福利厚生が充実している企業では、社員の成長をサポートする制度が整っており、スキルアップやキャリアアップを目指しやすくなります。
実際に働いていると、日々の業務に追われて新しいスキルを身につける余裕がないと感じる人も多いもの。しかし、企業が学習の機会を提供してくれる環境があれば、仕事をしながら効率よくスキルを磨くことが可能になります。
スキルアップ・キャリアアップを支援する福利厚生は以下の4つに分類されます。
資格取得支援制度:会社が資格試験の受験費用を補助し、合格時に報奨金を支給する制度。
例:TOEIC・簿記・マーケティング資格・プログラミング資格などの取得費用を会社が負担。
社内外研修制度:マネジメント・マーケティング・営業・ITスキルなど、業務に役立つ研修を受けられる。
オンライン学習:語学学習支援: 英会話スクールの費用補助、E-learningの無料受講など。
メンター制度・キャリアコーチング:上司や社外の専門家から、キャリアプランについてアドバイスを受けられる。
実際に簿記2級を取得すると、経理職の年収が平均50万円増加したというケースや実際に「基本情報技術者試験」や「Pythonエンジニア認定試験」を取得した社員が、社内SEにキャリアチェンジし、年収が70万円アップした事例もあります。
「職場で昇進できるかな?」「資格をとって給与をアップさせたい」と思っているなら、キャリアアップの福利厚生の充実度をチェックすることが重要です。昇進すれば、給与アップや裁量のあるポジションも期待できます!



資格試験の受験費用や参考書代も出してもらえるのはありがたい…!
【企業向け】福利厚生のメリット3選
福利厚生は、社員が快適に働ける環境を整え、仕事への満足度を高めるために欠かせないものです。充実した制度があると、働く人の生活がより豊かになり、会社にとっても良い影響をもたらします。ここでは、福利厚生の具体的なメリットを3つ紹介します。
メリット① 従業員の満足度向上と人材確保
福利厚生が充実していると、仕事だけでなくプライベートも充実しやすくなります。例えば、フレックスタイム制度やリモートワークを導入することで、通勤の負担が減り、自由に使える時間が増えます。その結果、社員のストレスが減り、働きやすさが向上します。
また、育児支援や住宅手当などのサポートが手厚い会社は、社員にとって「長く働きたい」と思える環境になります。特に、ワークライフバランスを大切にする人にとって、福利厚生が整っているかどうかは、転職を考える際の大きな判断基準となります。そのため、魅力的な福利厚生があると、優秀な人材を引き寄せ、長く働いてもらうことができるのです。
メリット② 会社のイメージが良くなり、信頼が高まる
福利厚生が充実している会社は、「社員を大切にしている企業」として世間から評価されます。特に、育児休暇の充実や、働き方改革に積極的な企業は求職者や取引先からの信頼を得やすくなります。
また、社員の健康や生活をサポートする制度があるとさらに企業の評価が高まります。
例えば、カフェテリアプラン(社員が自分に合った福利厚生を選べる制度)や、ジム・スポーツ施設の利用補助、資格取得支援などを取り入れることで、社員の働きやすさが向上し、企業のブランド価値もアップします。
このように、福利厚生は社員だけでなく、企業のイメージアップにも大きく貢献するのです。
メリット③ コスト削減につながり、会社の経営が安定する
福利厚生にはコストがかかると思われがちですが、長期的に見ると経費の節約にもつながります。例えば、健康診断や運動サポート制度を導入すると、社員の健康が維持され、病欠や医療費の負担が減る可能性があります。
また、研修制度を充実させることで、社員のスキルアップを促し、外部から新しい人材を採用するコストを抑えることもできます。
さらに、福利厚生がしっかりしている会社は、社員が長く働きやすくなるため、離職率が下がります。結果として、新しい人材の採用コストや教育コストを減らし、企業の安定した成長につながるのです。
メリットについてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください!
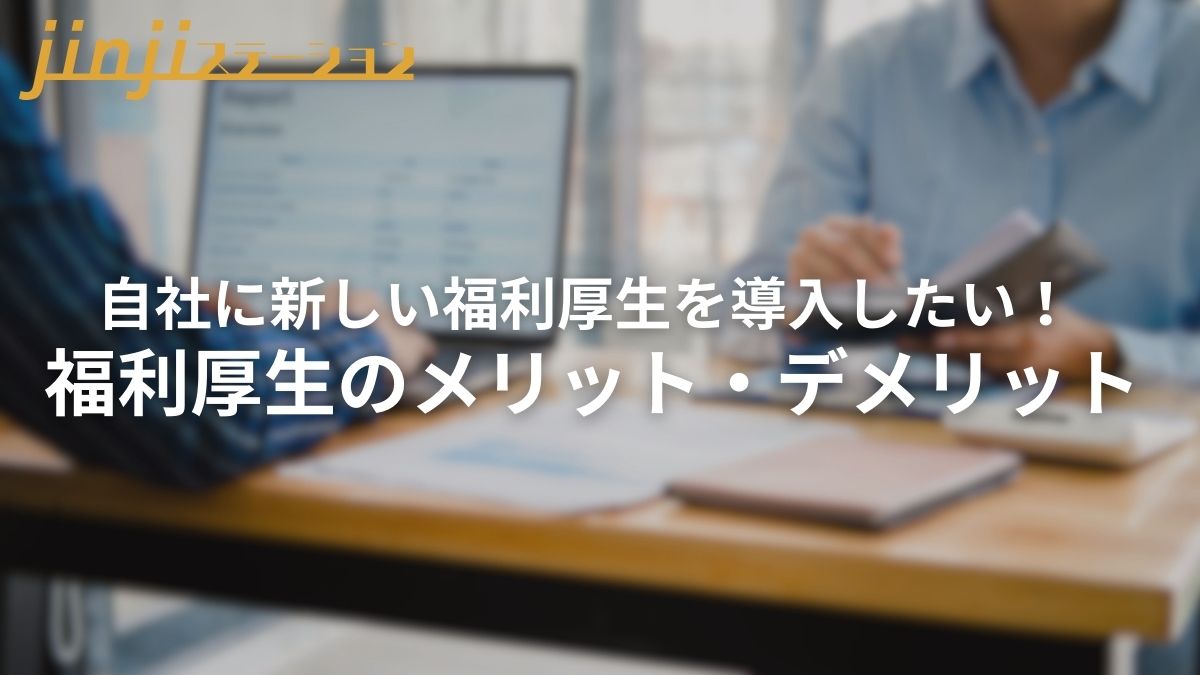
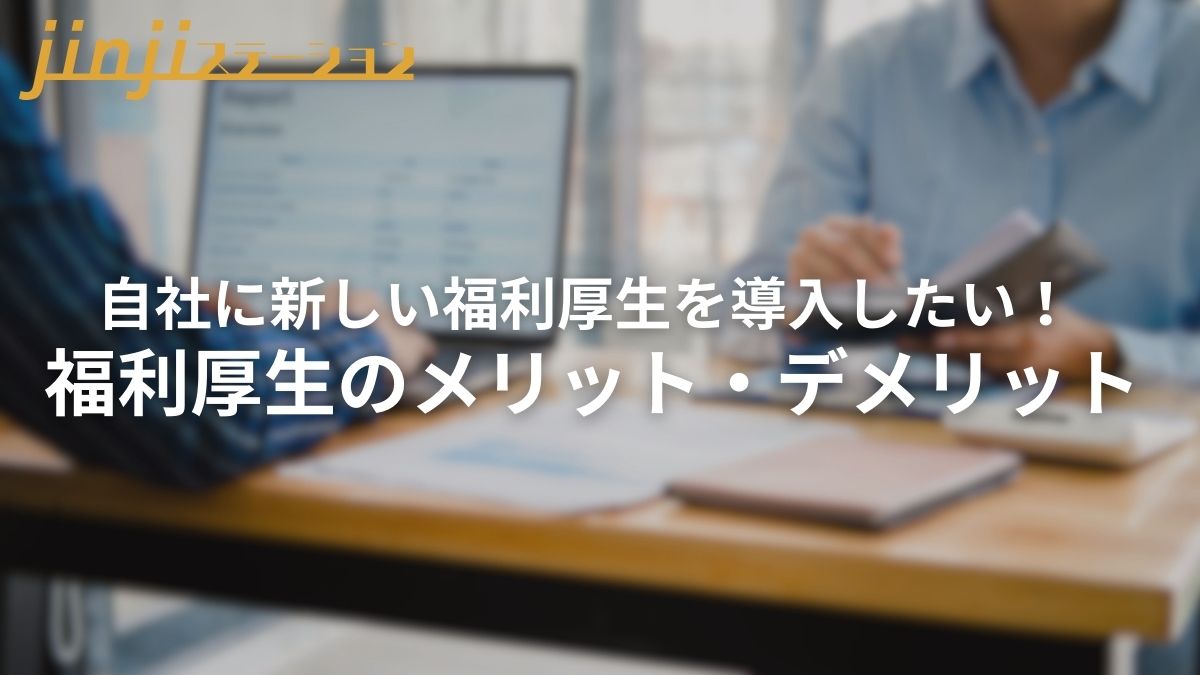
福利厚生を導入する前に知っておきたい3つの注意点
福利厚生は社員の働きやすさをサポートする一方で、意外なデメリットもあります。せっかく導入しても、うまく活用されなかったり会社に負担がかかりすぎたりすることも…。そこで、よくある問題点と、それを防ぐための対策を紹介します。
デメリット①効果がわかりにくい
福利厚生は、給与のように直接的な評価につながるものではないため、その効果をすぐに実感しにくいことがあります。
「本当に社員の満足度が上がっているのか?」「仕事の生産性が向上しているのか?」と、会社側が判断しづらいこともデメリットのひとつです。特に、経営陣が「コストに見合う価値があるのか」と疑問に思い、制度の縮小や廃止を検討することもあります。
こんな時は社員の声を定期的に集める機会を作ることが大切です。
アンケートや面談を通じて「どの制度が役立っているか?」を確認し、必要のないものは見直すとよいでしょう。また、離職率の変化や採用活動での反応など、間接的な指標をチェックするのも効果的です。
デメリット②従業員が望んでいないものを用意してしまう危険性
「社員のために」と思って導入した制度が、実際にはあまり使われず、ムダなコストになってしまうこともあります。たとえば、運動補助を目的にスポーツジムの割引制度を作っても、利用率が低いと意味がありません。せっかくの制度が社員のニーズとズレていると、「こんなのいらないのに…」と不満につながることも。
これを防ぐには、事前に社員の意見をしっかり聞くことが重要です。 「どんな福利厚生がほしいか?」をアンケートで集め、その結果をもとに、社員が本当に求めている制度を検討しましょう。
例えば、「書籍購入補助よりも、資格取得支援がほしい」という声が多ければ、専門資格の受験料補助やオンライン講座の受講支援など、より実用的な制度を導入できます。
また、導入後も定期的に利用状況をチェックし、必要に応じて見直すことが大切です。利用率が低い制度は、その理由をヒアリングし、内容の変更や別の制度への切り替えを検討しましょう。「使われない制度」を放置せず、常に改善を続けることで、社員にとって価値のある福利厚生を提供できます。
デメリット③管理の手間がかかる
福利厚生の種類が増えるほど、社内での運用管理の負担が大きくなるのが実情です。特に、資格取得支援制度や研修制度、ワークライフバランスを充実させるため福利厚生では、以下のような点を決める必要があります。
- どの資格を対象とするのか?
- 補助の上限をどう設定するのか?
- 旅行補助はどの範囲まで適用するのか?(家族も対象か、宿泊費のみか、交通費も含むか など)
- 申請手続きをどのように行うのか?
制度が増えるほど、人事・総務の管理業務が煩雑になり、社内での運用負担が増えてしまうことが課題です。また、外部の福利厚生サービスを利用する場合でも、契約や運用ルールの調整が必要になり、思ったよりも手間がかかるケースもあります。



自社で管理するのが難しい場合は福利厚生代行サービスで、運用の負担を減らすのもおすすめです!
福利厚生を導入する際の手順
福利厚生を取り入れるときは会社の目的や従業員の希望に合ったものを選ぶことが大切です。うまく導入できれば、働きやすい環境が整い社員の満足度アップや会社の魅力向上につながります。
今回は効果的な福利厚生を導入する際の手順をわかりやすく紹介します。
1. 導入目的と目標を明確にする
まず、「なぜ福利厚生を導入するのか」「どのような成果を期待するのか」を明確にします。
目的が曖昧なまま導入すると、コストだけがかかり効果が薄れるので注意が必要です。
例)従業員の定着率向上、ワークライフバランスの充実、業務効率の向上 など
2. 従業員のニーズを調査する
福利厚生は従業員のための制度なので、実際にどのような福利厚生があったら嬉しいかを知ることが大切です。
- アンケート調査を実施し、従業員の要望を収集する
- ヒアリングを通じて、具体的な意見を聞く
- 他社事例を参考にしつつ、自社の課題を洗い出す
3. ニーズに合った福利厚生を選定する
調査結果をもとに、導入する福利厚生を検討します。
ただし、すべての要望を実現するのは難しいため、以下の点を考慮して選定することが大切です。
- 予算内で実施可能か
- 企業の文化や方針に適しているか
- 長期的に運用可能か
4. 社内で情報を共有する
福利厚生の導入が決まったら、従業員にしっかりと情報を伝えることが重要です。導入側としては「制度を充実させた」と思っていても、従業員がその存在や利用方法を知らなければ意味がなく、十分に活用されない可能性があります。
そのため、社内メールやポータルサイトを活用して、どのような福利厚生が導入されたのかを周知することが大切です。
また、説明会を開いて直接制度の内容や利用方法を伝えたり、従業員が疑問を解消できるように質問対応窓口を設けたりするのも効果的です。制度の詳細をわかりやすく伝え、従業員がスムーズに利用できる環境を整えましょう。



「導入したから終わり」ではなく、「どうしたら従業員が使いやすくなるか」を考えながら、情報共有の仕方を工夫することが大切ですね。
5. 導入後の運用と定期的な見直し
福利厚生は、導入して終わりではなく、その後の運用と見直しが欠かせません。
まず、実際にどのくらいの従業員が利用しているのかを定期的にチェックし、期待していた効果が得られているかを確認する必要があります。
導入側が「良い制度だ」と考えていても、実際の利用率が低ければ、その原因を探る必要があります。例えば、「制度が知られていない」「利用の手続きが面倒」「そもそもニーズに合っていない」など、利用が進まない理由はいくつか考えられます。
また、「せっかくの制度だけど、実際に使う場面がない」「もっとこういう形なら使いやすいのに」といった従業員の生の声を集めることも重要です。アンケートを実施したり、ヒアリングの機会を設けたりして、「福利厚生が社員にとって本当に価値のあるものになっているか」を定期的に見直しましょう。
福利厚生を形だけのものにせず、実際に役立つ制度として機能させるために、定期的な改善を心がけましょう。
福利厚生代行サービスについて
一般的に企業の福利厚生サービスは「パッケージ型」と「カフェテリア型」の大きく2つに分類できます。また、この2つに加え、ハイブリッド型やオンデマンド型などの新しい形態の福利厚生サービスも増えつつあります。以下でそれぞれの特徴とメリットデメリットについて分かりやすく解説しています。
パッケージ型の代行サービス
あらかじめ決められた福利厚生メニューがセットとして全従業員に一律提供される方式で、多くの企業で採用されているシンプルな形態です。メニューが限られているので比較的導入コストが低く、管理が簡単というメリットがありますが、従業員の個別ニーズに対応する柔軟性が低いため、満足度が上がりにくいというデメリットも指摘されています。
カフェテリア型の代行サービス
従業員がメニューの中から自分に合ったサービスを自由に選べる方式で、特定のポイントや予算内で自由に福利厚生メニューを組み合わせられます。従業員の状況に応じた選択ができるため満足度は高まりやすいですが、導入コストや運用管理の負担が高くなる傾向があります。
カフェテリア型について詳しく知りたい方はぜひこちらの記事もご覧ください。
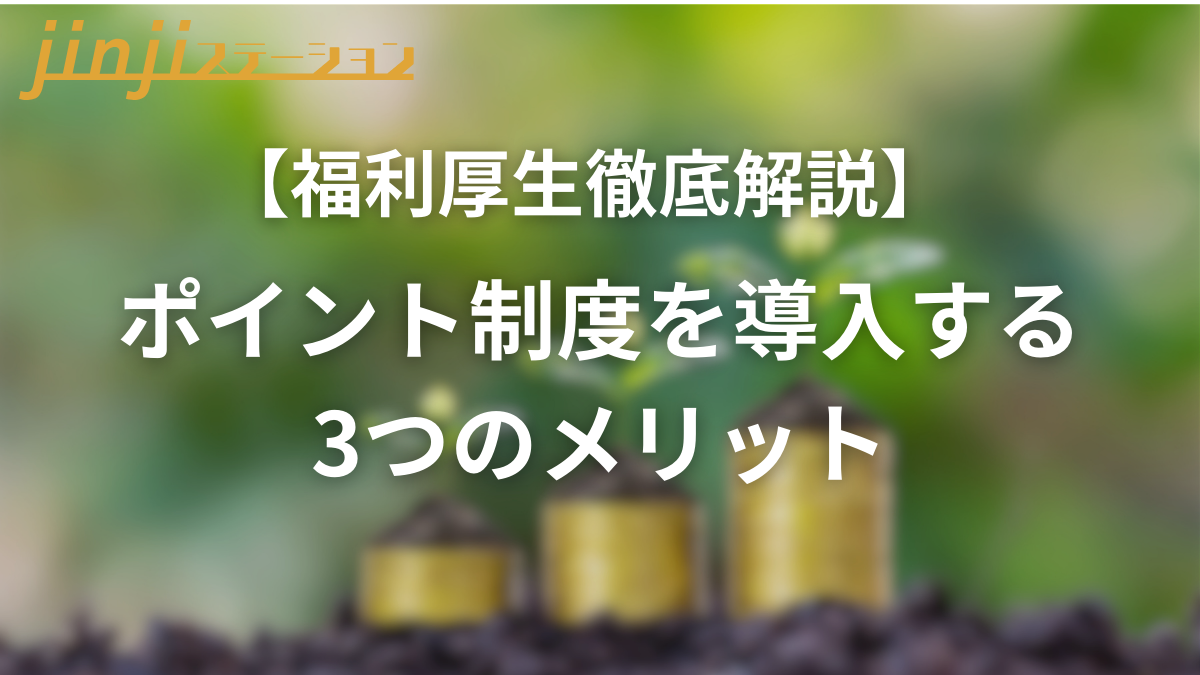
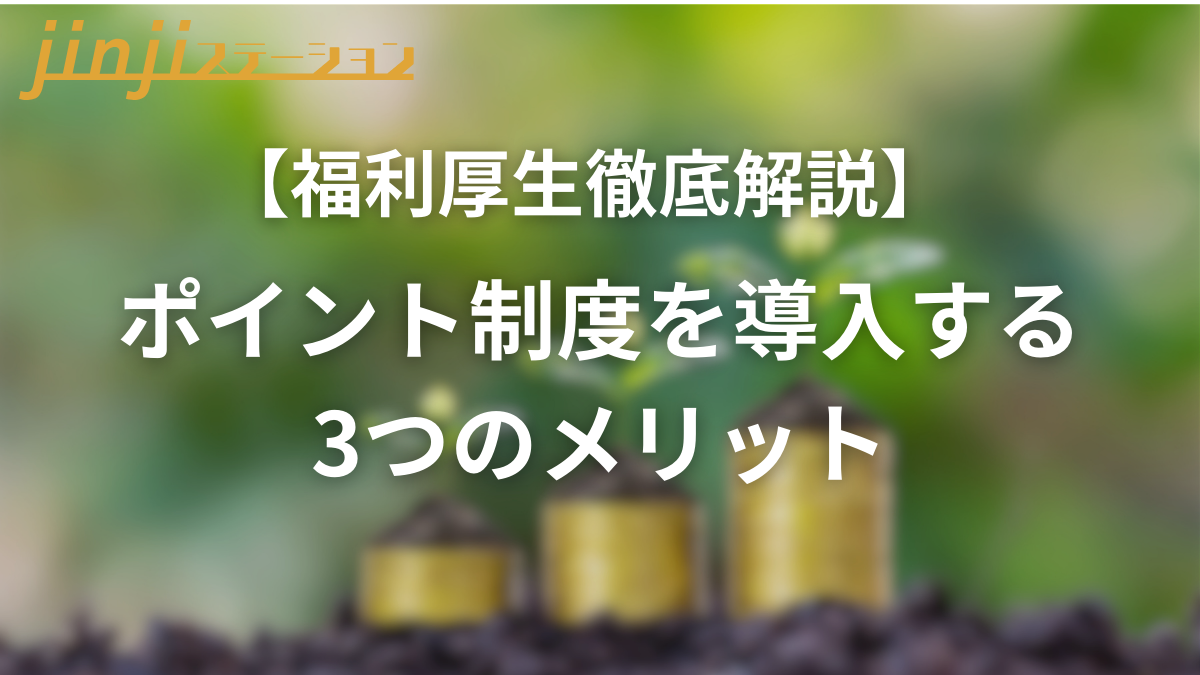
近年はハイブリッド型やオンデマンド型なども増えている!
上記で紹介した2つの方式が基本形ではありますが、最近はパッケージ型とカフェテリア型の良いところを組み合わせた「ハイブリッド型」や、特定のオンラインプラットフォームを通じて、必要なときに必要な福利厚生を提供する「オンデマンド型」の福利厚生も増えています。
| 福利厚生の型 | 特徴 | メリット | デメリット | イメージ例 |
| パッケージ型 | 一律の福利厚生メニューを全従業員に提供 | 導入や管理が簡単で、コストが抑えられる | 従業員の個々のニーズに対応しづらく、満足度が上がりにくい | 企業が医療保険や通勤費補助など基本的なサービスを全従業員に提供 |
| カフェテリア型 | 従業員がポイントでメニューを自由に選択 | 従業員が自分に合った福利厚生を選べるため満足度が高くなりやすい | システム構築や管理が複雑で、導入コストが高くなることもある | 毎月付与されるポイントで、従業員がジムや教育サポートなどを自由に選択 |
| ハイブリッド型 | パッケージ型とカフェテリア型を組み合わせ、基本と選択メニューを提供 | 基本的な福利厚生を全員に提供しつつ、選択肢も加えるため柔軟性が高く従業員満足度が上がりやすい | 運用コストや管理負担が増える可能性がある | 全従業員に医療保険と通勤費補助を提供しつつ、ポイントを使ってフィットネスや書籍購入などの福利厚生も選べる |
| オンデマンド型 | 必要な時に利用できるデジタルプラットフォームで福利厚生を提供 | 時間や場所を選ばず利用でき、従業員が自分のペースでサービスを活用できる | 初期費用が高く、利用頻度が低いと導入効果が感じにくい場合もある | アプリでオンラインカウンセリングやフィットネス動画、健康相談などをいつでも利用可能にし、従業員が自宅や通勤時間に活用できる |
人気の福利厚生代行サービス
人材確保や定着を図るために、多くの企業で独自の福利厚生を提供する動きが活発化しています。ここでは、社員が「あったらうれしい」と感じる、ユニークな福利厚生の事例をいくつかピックアップしてご紹介します。
食事系おすすめ福利厚生サービス
1.オフィスおかん
オフィスおかんとは「置き型社食®」を商標登録している株式会社OKANの福利厚生サービスです。導入に必要なものは、設置スペースと電子レンジのみで、手軽に社食を導入する事ができます。コンビニや弁当屋さんよりも手軽に食事がとれて、従業員は24時間いつでも“手軽でおいしい”と“栄養バランス”が両立した食事を摂りやすいことが特徴です。
| メリット・特徴 | 1. 24時間いつでも利用できる 2. 1食100円(税込)で利用できる(※1) 3. 管理栄養士が監修(※2) |
| 費用 | 初期費用:当サイト経由でお申込みいただければ初期費用0円 おかん便50:43,100円/月~ 月間納品数:50個/月~ |
※1 1品100円(税込)は想定利用価格です。
※2 レシピ等の内容や商品の選定の監督・指示を行うこと
詳しくはこちらの記事をご覧ください!





私も食べてますが、本当に美味しいです!
オフィスで野菜
オフィスに冷蔵庫(冷凍庫)を設置し、新鮮なサラダやフルーツ、こだわりのお惣菜など約140品の多彩なメニューを1つ100円から購入できる社食サービスです。ランチや間食など幅広いシーンで活用できます。新鮮なサラダやフルーツを楽しめる冷蔵プランと、日持ちが良く満足感の高い冷凍プランで、さまざまな食のニーズに対応しています。
| メリット・特徴 | 1. 大企業から中小企業まで、全国約500万人の従業員が利用している 2. 地産地消やサステナビリティを意識したサービス 3. お惣菜だけではなく、サラダやカットフルーツも選べる |
| 費用 | 要お問い合わせ |
詳しくはこちら:100円で食べられる設置型健康社食®



100円でサラダやフルーツが食べられるのは嬉しい!
スナックミーオフィス


snaq.me office (スナックミーオフィス)は、ヘルシーなお菓子やドリンク、そうざいなどを定期配送するサブスクリプション型の福利厚生サービスです。お菓子は、人工甘味料・合成香料・保存料を使用せず、厳選されたナチュラル素材のみで作られており、管理栄養士監修のもと、一日の間食のカロリー内に収まるよう設計されています。
設備不要・低コストで、全国どこでも導入できるため、数名規模の小規模オフィスから大企業まで幅広く利用されています。
| メリット・特徴 | 1.設備不要&低コストで、全国どこでも対応可能 2.100種類以上のバリエーションがあり、飽きずに楽しめる 3.AIが好みを学習し、企業ごとに最適なおやつBOXを提案 |
| 費用 | 初期・月額費用0円 コースについては要お問い合わせ 当サイト経由でお申し込みいただいた企業様限定で、スナックミーオリジナルのプロテインバーとスペシャルティコーヒーを無料プレゼント! |
詳しくはこちら:snaq.me office (スナックミーオフィス)|ヘルシーおやつの福利厚生↗



予算や規模に応じて柔軟にサポートしてくれるので、小規模オフィスにもおすすめ!
さらに詳しく、食事補助の福利厚生について知りたい方はこちら


旅行系福利厚生サービス
SANU 2nd Home
「SANU 2nd Home」は、都市生活者に「自然の中のもう一つの家」を提供するメンバーシップ制のセカンドホームサービスです。また、従業員が日常の忙しさから離れて、家族とゆっくり会話する時間を確保できるのも大きなメリットです。
| メリット・特徴 | 1.自然の中でリフレッシュできる 2.リーズナブルに休日を過ごせる 3.家族でゆっくり会話する時間が取れる 4.仕事とプライベートとの切り替えがしやすくなる |
| 費用 | 初期費用0円 年間30泊プラン:9万円/月額 年間60泊プラン:18万円/月額 年間90泊プラン:27万円/月額 |
詳しくは:自然の中にもう一つの家 SANU 2nd Home



リゾート系福利厚生の中ではコスパ最強!
東急ハーヴェストクラブ
東急不動産が運営する会員制リゾートホテルです。企業が福利厚生サービスとして導入することで、社員やその家族が全国各地のリゾート施設を利用できるようになります。社員のリフレッシュや家族との時間を大切にできるほか企業の魅力向上や採用活動の強化につなげることができます。
| メリット・特徴 | 1.全国の施設を利用できる 2.利用料金はオールシーズン同一料金 3.社員のご家族も同じ料金で利用できる |
| 費用 | ・1泊1名(税込) 5,500円(6,300円)13歳以上 4,400円(4,900円)4歳~12歳 客室タイプ別 1泊1室(税込) VIALA:17,200円~49,700円(VIALA会員料金) RESERVE:11,500円~28,800円(ホームグラウンド会員料金) |



土・日・祝日、いつでも同一料金で利用可能!
リゾートワークス
リゾートワークスは、全国のリゾートエリアにある会員制施設や一流ホテルを特別価格(通常の宿泊料金よりも30~80%割引)で利用できる会員制サービスです。
また、新幹線のチケットも最大30%割引で利用可能で、合宿や旅行時の交通費・宿泊費を削減し、手配の手間を省くこともできます。
| メリット・特徴 | 1.厳選された施設会員限定の特別価格で利用できる |
| 費用 | 1〜50人: 月額3.9万(2年契約):月額4.9万(1年契約) 51〜100人: 月額6.9万(2年契約):月額8.9万(1年契約) 101〜200人: 月額10.9万(2年契約):月額13.9万(1年契約) 201〜300人: 月額15万(2年契約):月額19万(1年契約) 300人: 要見積(2年契約):要見積(1年契約) |
詳しくはこちら:Resort Worx(リゾートワークス)↗



全国のホテルが最大80%オフになる!
従業員満足度の高い福利厚生サービス
ベネフィットステーション
ベネフィットステーションは、業界No.1の会員数を誇り、そのサービス数も140万以上と、日常で使える特典から研修支援まで幅広くサポートしてくれます。
また、Netflixプランなどの追加プランもあり、自社の状況に応じて、サービスを手厚くすることが可能です。
| 福利厚生の型 | カフェテリア型 |
| サービスの概要 | 健康支援、教育研修、エンタメ、給料特払いなど |
| メリット・特徴 | 1. 二親等まで使用できる約140万件以上の豊富なサービス 2. 人事担当の悩みである「従業員エンゲージメントの向上」「離職率に対するアプローチ」など様々な問題を一括で解決 |
| 費用 | 月額1人当たり1000円~1850円 |



二親等まで使えるのはとっても嬉しい!
Perk
Perkは、グルメ、映画、スキルアップ、レジャーなど幅広いジャンルのサービスを従業員・家族が法人優待価格で利用できる福利厚生サービスです。
1,000以上のサービスが利用可能で、ビジネススキルの向上からプライベートの充実まで幅広く従業員の多様なニーズに対応しています。簡単に導入でき、コストを抑えながら福利厚生を充実させられるため、50名~100名規模の会社に人気です。
| メリット・特徴 | 1. 1ヶ月あたりの利用サービス件数上限なし 2. 面倒な手続きが不要 3. 導入費用の負担ゼロ |
| ミニマムプラン費用 | 初期費用:0円 10名ごとの契約で一人当たり、280円~1250円/月※ 10人:一人当たり、1250円/月 50人:一人当たり、400円/月 100人〜:一人当たり、280〜400円/月 |
| 利用促進プラン費用 | 100人(月500P含む):一人当たり、975円/月 |
※プランはすべて12ヶ月契約となっています。
詳しくはこちらPerk(パーク)- 一人ひとりに挑むチカラを↗



コンビニやカラオケ、飲食チェーン、映画館など、社員が使いやすい福利厚生になっています!
さらに詳しく、福利厚生のトレンドについて知りたい方はこちら


まとめ
この記事では、福利厚生の基本から、導入の手順、人気の福利厚生代行サービスまで詳しく解説しました。
福利厚生は、従業員の働きやすさを向上させ、企業の魅力を高める重要な要素です。
しかし、導入や運用にはコストや管理の課題も伴います。そのため、 「どの福利厚生が自社に適しているのか?」 と悩む企業も多いのではないでしょうか?
そんなお悩みを持つ方はせひ弊社の無料コンシェルジュサービス をぜひご活用ください!
現在、 先着50社限定で、専門アドバイザーが企業の状況やニーズに合わせた 最適な福利厚生プラン をご提案いたします。
- 自社に最適な福利厚生が知りたい
- 他社と差別化できる福利厚生を導入したい
- 導入コストを抑えながら、効果的な制度を整えたい
こうしたお悩みをお持ちの方は、 無料コンシェルジュサービス を活用し、貴社にぴったりの福利厚生制度を見つけましょう!